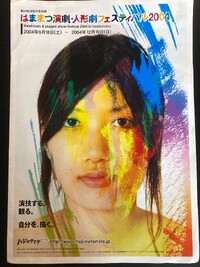2017年04月04日00:20
劇団からっかぜ 春の試演会~劇団員による書きおろし三作品一挙上演≫
カテゴリー │静岡県西部演劇連絡会会報原稿
■劇団からっかぜ 春の試演会~劇団員による書きおろし三作品一挙上演
フィールド 寺田景一
はままつ演劇・人形劇フェスティバルの劇作ワークショップでは、
毎回多くの短編戯曲が生まれる。
2010年に鹿目由紀さんを講師に迎えたワークショップを皮切りに
昨年2016年の平塚直隆さんの回まで7回に渡るので、
作品数としては、かなりの数になるだろう。
講師の方によるが、ワークショップを通して書き上げたそれぞれの作品が、
最終日に発表という形式で読み上げられる。
上演される、と言いたいところだが、配役を参加者たちに依頼し、
ほぼ初見で読み上げられた作品は、
やはり、「上演された」とは言い難い。
そして、書き上げられた作品から選抜された3~4本の戯曲は、
演技ワークショップの教材となる。
1日を通して芝居作りを学ぶという行程の中で、
その戯曲は、ワークショップの最後の発表で、披露される。
とはいえ、メインは演技ワークショップ参加者たちであるので、
参加者それぞれにセリフが与えられ一つの役が重複したり、
当然、衣装、小道具など上演に必要な処置が施されているわけではない。
最後に、フェスティバルのファイナルイベントにて、
有志の演出家・演技ワークショップの参加者により、
教材となった戯曲は上演される。
上演される、とは言ってみたが、
限られた稽古時間、制作のための予算がない中での上演となる。
劇作ワークショップで生まれた戯曲の役割は、
とりあえずはここで終わる。
そのあとの処遇は、個々に委ねられる。
自らの劇団の公演で、
短編作品集の一本として上演したという話を聞いたこともある。
ただし、ほとんどは、
それぞれのPCの中、もしく原稿用紙、プリントアウトの中に残されたまま、
中には削除、廃棄処分の場合もあるかもしれない。
戯曲の行く末を特別惜しむこともないが、
それぞれの戯曲は、書いた本人に帰結する。
そして、今回、先月3月5日の日曜日、
劇団からっかぜアトリエで
「春の試演会~劇団員による書きおろし三作品一挙上演」が14時開演で開かれた。
劇団からっかぜの劇団員である、
平井新さん、渡邉純子さん、高橋佑治さんが、
それぞれ劇作ワークショップに参加した折に書かれた戯曲を上演しようという試みである。
それぞれの作品は作者もしくは劇団員たちにより演出され、
劇団員たちがキャストにつく。
劇団の稽古場でもあり、上演場所でもあるアトリエで、
日々稽古が積み重ねられ、
役にふさわしい衣装をつけ、
小道具やセットが用意され、
音響効果や照明効果も施され、
集められた観客の前で上演される。
一旦本人に帰結した戯曲が、
再び、戯曲としての役割を果たした瞬間とも言える。
戯曲は文学作品として、書店や図書館にも並ぶが、
戯曲というものは、読むものではなく、上演されてこその戯曲だなあ、
とあらためて思った。(諸説あり)
ちなみに今回上演された作品は、
平井新作「あい棒」、
渡邉純子作「バッターボックス」、
高橋佑治作「あのとき、実は・・・」である。
了
(静岡県西部演劇連絡会会報 2017年4月2日号より)

フィールド 寺田景一
はままつ演劇・人形劇フェスティバルの劇作ワークショップでは、
毎回多くの短編戯曲が生まれる。
2010年に鹿目由紀さんを講師に迎えたワークショップを皮切りに
昨年2016年の平塚直隆さんの回まで7回に渡るので、
作品数としては、かなりの数になるだろう。
講師の方によるが、ワークショップを通して書き上げたそれぞれの作品が、
最終日に発表という形式で読み上げられる。
上演される、と言いたいところだが、配役を参加者たちに依頼し、
ほぼ初見で読み上げられた作品は、
やはり、「上演された」とは言い難い。
そして、書き上げられた作品から選抜された3~4本の戯曲は、
演技ワークショップの教材となる。
1日を通して芝居作りを学ぶという行程の中で、
その戯曲は、ワークショップの最後の発表で、披露される。
とはいえ、メインは演技ワークショップ参加者たちであるので、
参加者それぞれにセリフが与えられ一つの役が重複したり、
当然、衣装、小道具など上演に必要な処置が施されているわけではない。
最後に、フェスティバルのファイナルイベントにて、
有志の演出家・演技ワークショップの参加者により、
教材となった戯曲は上演される。
上演される、とは言ってみたが、
限られた稽古時間、制作のための予算がない中での上演となる。
劇作ワークショップで生まれた戯曲の役割は、
とりあえずはここで終わる。
そのあとの処遇は、個々に委ねられる。
自らの劇団の公演で、
短編作品集の一本として上演したという話を聞いたこともある。
ただし、ほとんどは、
それぞれのPCの中、もしく原稿用紙、プリントアウトの中に残されたまま、
中には削除、廃棄処分の場合もあるかもしれない。
戯曲の行く末を特別惜しむこともないが、
それぞれの戯曲は、書いた本人に帰結する。
そして、今回、先月3月5日の日曜日、
劇団からっかぜアトリエで
「春の試演会~劇団員による書きおろし三作品一挙上演」が14時開演で開かれた。
劇団からっかぜの劇団員である、
平井新さん、渡邉純子さん、高橋佑治さんが、
それぞれ劇作ワークショップに参加した折に書かれた戯曲を上演しようという試みである。
それぞれの作品は作者もしくは劇団員たちにより演出され、
劇団員たちがキャストにつく。
劇団の稽古場でもあり、上演場所でもあるアトリエで、
日々稽古が積み重ねられ、
役にふさわしい衣装をつけ、
小道具やセットが用意され、
音響効果や照明効果も施され、
集められた観客の前で上演される。
一旦本人に帰結した戯曲が、
再び、戯曲としての役割を果たした瞬間とも言える。
戯曲は文学作品として、書店や図書館にも並ぶが、
戯曲というものは、読むものではなく、上演されてこその戯曲だなあ、
とあらためて思った。(諸説あり)
ちなみに今回上演された作品は、
平井新作「あい棒」、
渡邉純子作「バッターボックス」、
高橋佑治作「あのとき、実は・・・」である。
了
(静岡県西部演劇連絡会会報 2017年4月2日号より)