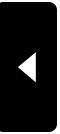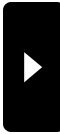2024年03月23日09:59
穂の国とよはし芸術劇場PLATで市民と創造する演劇「地を渡る舟」を観た≫
カテゴリー │演劇
3月2日(土)14時30分~
アフタートークに、作者の長田育恵さん、演出の扇田拓也さんが登壇した。
話を聞くのは、劇場の芸術文化プロデューサーである矢作勝義さん。
今回の「市民と創造する演劇」の題材に「地を渡る舟」を提案したのは、劇場側だと言う。
演出の扇田さんは、過去、長田さん主宰のてがみ座でこの演目を2度演出した。
上演時間150分の演目の提案に、扇田さんは驚いたと言う。
市民の方が参加する劇として、ハードルが高いと思うのも無理はない。
ただし、何年も市民劇を企画している劇場側は、経験から知っている。
市民の人たちがどれほどのことが出来るかを。
上演時間の長さなど大きな問題ではないのだ。
主要登場人物のセリフの多さは、心配するほどのものではない。
演劇をやりたい、
演劇の専門家(プロ)と共に、作り上げたい、
という思いで、応募してきた市民の方々なのだ。
初めて参加される方ばかりではないだろう。
何度か目の方が、経験のない方をサポートしたり、
互いに協力し合う形も自然と出来てくるだろう。
舞台美術として、時代物の民具が上からぶら下がっている。
渋沢栄一の孫である渋沢敬三が、自宅に仲間と集めた郷土玩具や化石を展示した小さな博物館アチック・ミューゼアムは、
若手研究者が集い、名もなき人、漁民や農民の民具を集め研究する場所となっている。
舞台美術に使われている民具は、呼びかけて、市民の方々から提供いただいた物だと言う。
この過程は、とても市民劇らしい。
“演劇”とは直接関係のないような方々が、協力し、
「納屋に、捨てないでたくさん残ってっけど、使いたいっていうんなら、どうぞどうぞ」
などという声が聞こえてくる気がするのだ。
「忘れられた日本人」などを書いた民俗学者・宮本常一の評伝でもあるが、
アチック・ミューゼアムを舞台にした群像劇で、
それぞれの登場人物に等分にスポットが当てられている。
ミューゼアムの主宰者である渋沢。
妻は三菱財閥の岩﨑家出身。
ミューゼアムの研究者たちはそれぞれ研究テーマが違い、東大出身のエリートが多いが、そこに劣等感を抱く立場の者もいる。
渋沢家で働く女中頭と見習い女中。
宮本常一夫妻。
調査協力で出入りするドヤ街出身の女性。
宮本が調査で出向いた先で出会う農民。
そして、陸軍の軍人。
それらステイタスや立場や思いが違う登場人物を役を担った市民たちは演じ分ける。
演劇が経過する時間の中には、
1939年、第二次世界大戦に突入し、1945年、戦争が終わるまでが含まれる。
映画でも小説でも演劇でも、近代史を取り上げることは、日本が直接関わった最後の戦争のことを描くと言うこと。
直截的に描かなくても、どこかしこに忍び込んでいる。
この作品では、戦争による変化を大きなテーマだ。
適性語とされアチック・ミューゼアムは、日本常民文化研究会と名を変える。
ただし、その名には、普通の人たちの文化を研究する場所と言う会の思いを託す。
同じ年齢の若者が戦地に出向く中、自分たちばかりが研究をしていていいのかと言う葛藤。
これは、大きな自然災害の後、自分の仕事が果たして必要なものなのだろうかと考え直す現象と似ている。
これは起こるたびに同じことを繰り返す。
渋沢は戦時下、日本銀行副総裁に、時の総理、東条英機より任ぜられる。
戦争の一方的な被害者である常民の生活を研究する学問を侵されようとしている中、抵抗するが立場上受けざるを得ない。
ただし、世間的には大出世で、彼は後に総裁、貴族院議員、経済人として活動する。
僕が新鮮に思ったのが、終戦により、三菱財閥出身の渋沢の妻、誉子が、財閥解体により、財産を取り上げられる覚悟を夫から聞かれ、戸惑うところ。
考えてみれば、「持ちすぎていた人」が、「それでもたくさん持っている人」に変わるだけなので、
今まで実感を持って感じなかったのかもしれないが、
あまりこういう場面観たことなかったかもと思った。
そう感じたのも、クールなお嬢さんであるが、自分を持ち、夫を支える妻の役を、俳優が的確に演じていたからかもしれない。
宮本常一の評伝として考えると、
戦争の影響が強くて(これは無理もない)、仕事を中心とする自身の生き方に焦点が定まりにくい所はあったかもしれない。
しかし、そもそも宮本常一は、そんなに題材として取り上げられることが多い人物ではない。
大河ドラマとか、歴史映画、歴史小説でも。
民俗学でも今回の演劇でも名が出てくる「遠野物語」の柳田國男は聞いたことがあっても、
宮本常一の名は聞いたことがない、という方も多いのではないか?
(僕にしても何年か前だ)
ただし、今回の市民劇にとっては、各登場人物にスポットがあたっていることが良かったと思う。
また、宮本常一も、身近な登場人物であるひとりの民俗研究者として、観客に受け入れられたのではないか?
それが、研究対象である「名もなき人」、つまり多くの市民たちと結びつき、市民劇であることの価値を生み出していく。
その成果のひとつが、市民の納屋、倉庫、住居から、私有の古い民具を引っ張り出したことではないかと思う。
それらはロビーに、参加者の制作の経過を写したパネルとポスターの中に、集まった民具の一部が展示されていた。
開演前、作者の長田さんが訪れ、それらを愛おしそうに眺めていた。
重要な役割は主要キャストだけではない。
普段は黒子、コロス、群衆、通行人、その他大勢などと言われる役にもきっちり目を配り、
というか、重要な役割としてスポットを当てるくらいの起用の仕方をされていた。
前半、登場する時の、うつむき、地面を眺め、腰が曲がった、低姿勢の、いかにも卑屈な姿、歩き方。
対して、ラストの、頭を上げ、腰を伸ばし、前や上を向き、いかにも前途洋々な姿、行動。
「名もなき人」それぞれの自分自身を語り、演じる。
もうひとつ、やはり音楽が良かった。
開演前の舞台では、すでに音が奏でられ、それらの体裁はミュージシャンではなく、そこに住む人。
生活の中で、音を出しているという、演出。
音楽担当の棚橋寛子さんは、SPAC(静岡県舞台芸術センター)の多くの宮城聰さん演出作品でもおなじみ。
ただし、ギターやヴァイオリンも使用され、それらとはまた違う音楽を感じることが出来た。

アフタートークに、作者の長田育恵さん、演出の扇田拓也さんが登壇した。
話を聞くのは、劇場の芸術文化プロデューサーである矢作勝義さん。
今回の「市民と創造する演劇」の題材に「地を渡る舟」を提案したのは、劇場側だと言う。
演出の扇田さんは、過去、長田さん主宰のてがみ座でこの演目を2度演出した。
上演時間150分の演目の提案に、扇田さんは驚いたと言う。
市民の方が参加する劇として、ハードルが高いと思うのも無理はない。
ただし、何年も市民劇を企画している劇場側は、経験から知っている。
市民の人たちがどれほどのことが出来るかを。
上演時間の長さなど大きな問題ではないのだ。
主要登場人物のセリフの多さは、心配するほどのものではない。
演劇をやりたい、
演劇の専門家(プロ)と共に、作り上げたい、
という思いで、応募してきた市民の方々なのだ。
初めて参加される方ばかりではないだろう。
何度か目の方が、経験のない方をサポートしたり、
互いに協力し合う形も自然と出来てくるだろう。
舞台美術として、時代物の民具が上からぶら下がっている。
渋沢栄一の孫である渋沢敬三が、自宅に仲間と集めた郷土玩具や化石を展示した小さな博物館アチック・ミューゼアムは、
若手研究者が集い、名もなき人、漁民や農民の民具を集め研究する場所となっている。
舞台美術に使われている民具は、呼びかけて、市民の方々から提供いただいた物だと言う。
この過程は、とても市民劇らしい。
“演劇”とは直接関係のないような方々が、協力し、
「納屋に、捨てないでたくさん残ってっけど、使いたいっていうんなら、どうぞどうぞ」
などという声が聞こえてくる気がするのだ。
「忘れられた日本人」などを書いた民俗学者・宮本常一の評伝でもあるが、
アチック・ミューゼアムを舞台にした群像劇で、
それぞれの登場人物に等分にスポットが当てられている。
ミューゼアムの主宰者である渋沢。
妻は三菱財閥の岩﨑家出身。
ミューゼアムの研究者たちはそれぞれ研究テーマが違い、東大出身のエリートが多いが、そこに劣等感を抱く立場の者もいる。
渋沢家で働く女中頭と見習い女中。
宮本常一夫妻。
調査協力で出入りするドヤ街出身の女性。
宮本が調査で出向いた先で出会う農民。
そして、陸軍の軍人。
それらステイタスや立場や思いが違う登場人物を役を担った市民たちは演じ分ける。
演劇が経過する時間の中には、
1939年、第二次世界大戦に突入し、1945年、戦争が終わるまでが含まれる。
映画でも小説でも演劇でも、近代史を取り上げることは、日本が直接関わった最後の戦争のことを描くと言うこと。
直截的に描かなくても、どこかしこに忍び込んでいる。
この作品では、戦争による変化を大きなテーマだ。
適性語とされアチック・ミューゼアムは、日本常民文化研究会と名を変える。
ただし、その名には、普通の人たちの文化を研究する場所と言う会の思いを託す。
同じ年齢の若者が戦地に出向く中、自分たちばかりが研究をしていていいのかと言う葛藤。
これは、大きな自然災害の後、自分の仕事が果たして必要なものなのだろうかと考え直す現象と似ている。
これは起こるたびに同じことを繰り返す。
渋沢は戦時下、日本銀行副総裁に、時の総理、東条英機より任ぜられる。
戦争の一方的な被害者である常民の生活を研究する学問を侵されようとしている中、抵抗するが立場上受けざるを得ない。
ただし、世間的には大出世で、彼は後に総裁、貴族院議員、経済人として活動する。
僕が新鮮に思ったのが、終戦により、三菱財閥出身の渋沢の妻、誉子が、財閥解体により、財産を取り上げられる覚悟を夫から聞かれ、戸惑うところ。
考えてみれば、「持ちすぎていた人」が、「それでもたくさん持っている人」に変わるだけなので、
今まで実感を持って感じなかったのかもしれないが、
あまりこういう場面観たことなかったかもと思った。
そう感じたのも、クールなお嬢さんであるが、自分を持ち、夫を支える妻の役を、俳優が的確に演じていたからかもしれない。
宮本常一の評伝として考えると、
戦争の影響が強くて(これは無理もない)、仕事を中心とする自身の生き方に焦点が定まりにくい所はあったかもしれない。
しかし、そもそも宮本常一は、そんなに題材として取り上げられることが多い人物ではない。
大河ドラマとか、歴史映画、歴史小説でも。
民俗学でも今回の演劇でも名が出てくる「遠野物語」の柳田國男は聞いたことがあっても、
宮本常一の名は聞いたことがない、という方も多いのではないか?
(僕にしても何年か前だ)
ただし、今回の市民劇にとっては、各登場人物にスポットがあたっていることが良かったと思う。
また、宮本常一も、身近な登場人物であるひとりの民俗研究者として、観客に受け入れられたのではないか?
それが、研究対象である「名もなき人」、つまり多くの市民たちと結びつき、市民劇であることの価値を生み出していく。
その成果のひとつが、市民の納屋、倉庫、住居から、私有の古い民具を引っ張り出したことではないかと思う。
それらはロビーに、参加者の制作の経過を写したパネルとポスターの中に、集まった民具の一部が展示されていた。
開演前、作者の長田さんが訪れ、それらを愛おしそうに眺めていた。
重要な役割は主要キャストだけではない。
普段は黒子、コロス、群衆、通行人、その他大勢などと言われる役にもきっちり目を配り、
というか、重要な役割としてスポットを当てるくらいの起用の仕方をされていた。
前半、登場する時の、うつむき、地面を眺め、腰が曲がった、低姿勢の、いかにも卑屈な姿、歩き方。
対して、ラストの、頭を上げ、腰を伸ばし、前や上を向き、いかにも前途洋々な姿、行動。
「名もなき人」それぞれの自分自身を語り、演じる。
もうひとつ、やはり音楽が良かった。
開演前の舞台では、すでに音が奏でられ、それらの体裁はミュージシャンではなく、そこに住む人。
生活の中で、音を出しているという、演出。
音楽担当の棚橋寛子さんは、SPAC(静岡県舞台芸術センター)の多くの宮城聰さん演出作品でもおなじみ。
ただし、ギターやヴァイオリンも使用され、それらとはまた違う音楽を感じることが出来た。