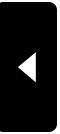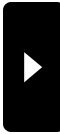2023年11月14日21:38
掌編小説『海へと向かうバスに乗る』を書いた≫
カテゴリー │掌編小説
JR浜松駅の北口前に、バスターミナルがある。
1~16番までのバス乗り場があり、
発着所となっている。
浜松の中心街までバスで買い物や遊びに来た場合、
帰りはまた、同じ乗り場からバスに乗るだろう。
お母さんと一緒に街に来た小学三年の男の子が帰る時、
違う乗り場のバスに乗ってしまう話。
『海へと向かうバスに乗る』
寺田景一
この街の駅前に、市内のあちこちから路線バスがやってくるターミナルがある。
停留所がいくつもあり、発着点となったり、終着点となったり、他の路線へつながる経由点となったりする。
小学三年生の森田建樹(もりたたてき)は、母とふたりでひとつの停留所の前にいた。
「トイレ行く?」
「いや、いい」
「そう。ちょっと待っててね」
母がそばを離れたのを見届けると、建樹は違う停留所に停まっているバスに乗りこんだ。
行先などわからない、初めて乗るバスだった。
トイレから母が戻ると、建樹を乗せたバスはすでにブロロンと音を立てて、出発していた。
父は建樹が幼い時に海で死んだ。
だから、母は好きだった海が嫌いになった。
建樹を連れて行くこともない。
母はスーパーマーケットで、建樹を育てるために、残業も厭わず働いている。
忙しい中、たまに日曜日が休みになると、建樹を街中へ連れ出した。
バスに乗って街中へ行き、子どもが気に入るような映画を観て、デパートで子どもが好きな物を食べる。
この日は人気のアニメ映画を観て、暑くなってきたからと、建樹だけ食後にかき氷を食べた。
間違いなく母が観たい映画じゃないし、その時、母は自分が好きな物を食べているのだろうか。
建樹は知っている。
母が、建樹が寝静まるのを確認した後、ひとりで泣いていることを。
窓の外から洩れる明かりが母の涙を映し出す。
建樹は目をそっと開け、その涙を見つめている。
建樹は母とふたりで出歩くのが嫌いだった。
出会う人が、哀れな親子を気の毒そうに見つめているように感じる。
建樹は人の視線を避けるように歩く。背中を丸め、地面を睨んだまま。
たまに人とぶつかるが、そんなことには構わない。
映画を観ていても内容は頭に入らないし、レストランで食べている物の味もわからない。
建樹は違うバスに乗って、母から逃げ出したのだ。
バスの中は静かだった。
夕方に差し掛かり、それぞれ楽しかった日曜の疲れがどっと押し寄せたように車内全体がぐったりしていた。
家族連れも、若い人も、年をとった人も。みんな目をつぶり、眠り込んでいるようだった。
制帽を几帳面に被った男性の運転手は、背中を向け、乗客のことなど気にしないかのように黙々とハンドルを握っている。
真ん中あたりの通路側に座っていた建樹にとっては都合が良かった。
母からひとり離れ、知らないどこかに向かう小学生であるとは思われないだろう。
だから、疑われないように、より平静を装った。
知っている場所に向かうために、乗り慣れたバスに乗っているのだ。
そう言い聞かせながら。
そっとポケットの上から財布を握り、乗車料を払う小銭が入っていることだけは、確認した。
いくつか停留所を通り過ぎ、何人か降りていった。
建樹は窓から外を見ようとするが、隣の眠っている中年の男に気付き、目を戻す。
「変わろうか」
男が突然建樹に話しかける。
「この先、海が見えるよ」
建樹はこのバスが海に向かっていることを知らなかった。
「大丈夫です」
建樹は海になどまったく興味がないようにふるまう。
特別ではない《いつものバス》なのだから。
男はそれ以上話しかけてこなかった。
建樹は海があるところでバスを降りよう、と心に決める。
隣の人を気にしながらも、あたりに海の気配はないかと集中する。
正面や反対側の窓から見える景色に、海を察するヒントはないか。
窓が開いていれば、潮の香りがするのにと、空調機をうらめしそうに見上げる。
隣の男は降りて行った。
建樹はその席に移動し、窓から外をながめる。
海の気配はなかった。
乗客たちは降りる場所が近づくと、気がついたようにつむっていた目を開け、ひとり、またひとりと降りて行く。
そして、車内は建樹と運転手だけになる。
運転手は相変わらず後ろ姿だけを建樹に向けている。
大きなルームミラーから顔が見えないかと体をよじったが、よくわからなかった。
外からの光で反射しているのかもしれないし、もしかしたら、顔などないのかもしれない。
とたんに、さびしい気持ちになった。
この世でひとりきり。
「僕はどこへ向かうのだろうか」
海に向かっていることも消えていた。
窓の外はどこにでもある代わり映えのない景色なのに、やけに見知らぬ場所のような気がした。
オレンジの太陽だけが、急速に落ちて行くように見えた。
暗闇へ。
ひとり暗闇の世界へ。
そう思ったら、突然涙が出てきた。涙は止まらない。
ただ、顔のない運転手には気づかれないようにした。
声を押し殺し、ただただ涙があふれ出た。
そして、思わず叫びそうになる。
「お父さん」
声は出なかった。
「海が見えるよ」
その声は確かに建樹には聞こえた。
「ちょうど日が暮れる時間だ」
言葉を発しているのは、背中を向けた運転手だった。
ルームミラーには、にこやかに笑う口元が映っている。
「建樹君、もうすぐ終点だ。お母さんが待ってるよ」
母がバス会社に建樹がいなくなったことを連絡していた。
各運転手に通知が行き、ひとりで乗っている建樹の顔や背格好、出で立ちを確認し、母は自分の車で先回りしたのだ。
建樹の涙は乾かなかった。
すぐに現れた夕焼けに染まった海をながめても、それは変わらない気がした。

1~16番までのバス乗り場があり、
発着所となっている。
浜松の中心街までバスで買い物や遊びに来た場合、
帰りはまた、同じ乗り場からバスに乗るだろう。
お母さんと一緒に街に来た小学三年の男の子が帰る時、
違う乗り場のバスに乗ってしまう話。
『海へと向かうバスに乗る』
寺田景一
この街の駅前に、市内のあちこちから路線バスがやってくるターミナルがある。
停留所がいくつもあり、発着点となったり、終着点となったり、他の路線へつながる経由点となったりする。
小学三年生の森田建樹(もりたたてき)は、母とふたりでひとつの停留所の前にいた。
「トイレ行く?」
「いや、いい」
「そう。ちょっと待っててね」
母がそばを離れたのを見届けると、建樹は違う停留所に停まっているバスに乗りこんだ。
行先などわからない、初めて乗るバスだった。
トイレから母が戻ると、建樹を乗せたバスはすでにブロロンと音を立てて、出発していた。
父は建樹が幼い時に海で死んだ。
だから、母は好きだった海が嫌いになった。
建樹を連れて行くこともない。
母はスーパーマーケットで、建樹を育てるために、残業も厭わず働いている。
忙しい中、たまに日曜日が休みになると、建樹を街中へ連れ出した。
バスに乗って街中へ行き、子どもが気に入るような映画を観て、デパートで子どもが好きな物を食べる。
この日は人気のアニメ映画を観て、暑くなってきたからと、建樹だけ食後にかき氷を食べた。
間違いなく母が観たい映画じゃないし、その時、母は自分が好きな物を食べているのだろうか。
建樹は知っている。
母が、建樹が寝静まるのを確認した後、ひとりで泣いていることを。
窓の外から洩れる明かりが母の涙を映し出す。
建樹は目をそっと開け、その涙を見つめている。
建樹は母とふたりで出歩くのが嫌いだった。
出会う人が、哀れな親子を気の毒そうに見つめているように感じる。
建樹は人の視線を避けるように歩く。背中を丸め、地面を睨んだまま。
たまに人とぶつかるが、そんなことには構わない。
映画を観ていても内容は頭に入らないし、レストランで食べている物の味もわからない。
建樹は違うバスに乗って、母から逃げ出したのだ。
バスの中は静かだった。
夕方に差し掛かり、それぞれ楽しかった日曜の疲れがどっと押し寄せたように車内全体がぐったりしていた。
家族連れも、若い人も、年をとった人も。みんな目をつぶり、眠り込んでいるようだった。
制帽を几帳面に被った男性の運転手は、背中を向け、乗客のことなど気にしないかのように黙々とハンドルを握っている。
真ん中あたりの通路側に座っていた建樹にとっては都合が良かった。
母からひとり離れ、知らないどこかに向かう小学生であるとは思われないだろう。
だから、疑われないように、より平静を装った。
知っている場所に向かうために、乗り慣れたバスに乗っているのだ。
そう言い聞かせながら。
そっとポケットの上から財布を握り、乗車料を払う小銭が入っていることだけは、確認した。
いくつか停留所を通り過ぎ、何人か降りていった。
建樹は窓から外を見ようとするが、隣の眠っている中年の男に気付き、目を戻す。
「変わろうか」
男が突然建樹に話しかける。
「この先、海が見えるよ」
建樹はこのバスが海に向かっていることを知らなかった。
「大丈夫です」
建樹は海になどまったく興味がないようにふるまう。
特別ではない《いつものバス》なのだから。
男はそれ以上話しかけてこなかった。
建樹は海があるところでバスを降りよう、と心に決める。
隣の人を気にしながらも、あたりに海の気配はないかと集中する。
正面や反対側の窓から見える景色に、海を察するヒントはないか。
窓が開いていれば、潮の香りがするのにと、空調機をうらめしそうに見上げる。
隣の男は降りて行った。
建樹はその席に移動し、窓から外をながめる。
海の気配はなかった。
乗客たちは降りる場所が近づくと、気がついたようにつむっていた目を開け、ひとり、またひとりと降りて行く。
そして、車内は建樹と運転手だけになる。
運転手は相変わらず後ろ姿だけを建樹に向けている。
大きなルームミラーから顔が見えないかと体をよじったが、よくわからなかった。
外からの光で反射しているのかもしれないし、もしかしたら、顔などないのかもしれない。
とたんに、さびしい気持ちになった。
この世でひとりきり。
「僕はどこへ向かうのだろうか」
海に向かっていることも消えていた。
窓の外はどこにでもある代わり映えのない景色なのに、やけに見知らぬ場所のような気がした。
オレンジの太陽だけが、急速に落ちて行くように見えた。
暗闇へ。
ひとり暗闇の世界へ。
そう思ったら、突然涙が出てきた。涙は止まらない。
ただ、顔のない運転手には気づかれないようにした。
声を押し殺し、ただただ涙があふれ出た。
そして、思わず叫びそうになる。
「お父さん」
声は出なかった。
「海が見えるよ」
その声は確かに建樹には聞こえた。
「ちょうど日が暮れる時間だ」
言葉を発しているのは、背中を向けた運転手だった。
ルームミラーには、にこやかに笑う口元が映っている。
「建樹君、もうすぐ終点だ。お母さんが待ってるよ」
母がバス会社に建樹がいなくなったことを連絡していた。
各運転手に通知が行き、ひとりで乗っている建樹の顔や背格好、出で立ちを確認し、母は自分の車で先回りしたのだ。
建樹の涙は乾かなかった。
すぐに現れた夕焼けに染まった海をながめても、それは変わらない気がした。

この記事へのコメント
突然のレス失礼します。
ご無沙汰しちゃいました。
実は過日ステーキをご一緒したのち、またまた本当に忙しくて、
なぜそんなにまで忙しいかというと、
やはりサウナに莫大な時間を取られるのも一因です。
本当に1日3.5-4時間しか寝ていません。
ステーキの後、すぐに連絡しようと思っていましたが
すっかりタイミングを逸してしまいました。
いくら何ても超短眠のツケが出てしまいました。
8月冒頭、何とコロナにかかってしまいました。
あれだけ絶大な自己免疫力を信じていたのに、晴天の霹靂でした。
医師に一切の薬は要らない、自己免疫で直るから、と申し出て
「解りました。でも少しでも苦しくなったら躊躇せず(私が一人暮らしなのを知っているので)救急車を呼んでくれと。
38.2℃ありましたが、こんな熱24時間以内に自己免疫で直る
体が必要としている体温を解熱剤で下げるのは愚の骨頂でしょうと。
次の日に最高39.6まで上がりほんの少し焦りましたが
体は別にそれほど苦しくないし、食欲は有るし、におい香りも敏感だ
そうだ、車でサウナは欠かしてはならない !!
さすがに24時間以内には体温がさがらなかったのですが
丸2日後には見事に36.6(平熱)になりました。
負け惜しみかもしれませんが、まだまだ俺の免疫力は凄いな、と思いました。
ところで・・・
テトラさんと(ステーキ前後も含めて)数年コンタクトが無かったので
私は、すっかり、テトラさんは普通の人間なのだと認識していました。
それは間違いでした。
此処の投稿の「寺田景市」さんの文章に触れ
これだけの長文にもかかわらず見事に展開・構成されている、
こんな文章を日常的にいつも掻けるのはやはり「普通の人間」では無いなと。
少なくても私には絶対に出来ません。
今後とも断片的なコンタクトになってしまうと思いますが
何卒よろしくお願い申し上げます。
ご無沙汰しちゃいました。
実は過日ステーキをご一緒したのち、またまた本当に忙しくて、
なぜそんなにまで忙しいかというと、
やはりサウナに莫大な時間を取られるのも一因です。
本当に1日3.5-4時間しか寝ていません。
ステーキの後、すぐに連絡しようと思っていましたが
すっかりタイミングを逸してしまいました。
いくら何ても超短眠のツケが出てしまいました。
8月冒頭、何とコロナにかかってしまいました。
あれだけ絶大な自己免疫力を信じていたのに、晴天の霹靂でした。
医師に一切の薬は要らない、自己免疫で直るから、と申し出て
「解りました。でも少しでも苦しくなったら躊躇せず(私が一人暮らしなのを知っているので)救急車を呼んでくれと。
38.2℃ありましたが、こんな熱24時間以内に自己免疫で直る
体が必要としている体温を解熱剤で下げるのは愚の骨頂でしょうと。
次の日に最高39.6まで上がりほんの少し焦りましたが
体は別にそれほど苦しくないし、食欲は有るし、におい香りも敏感だ
そうだ、車でサウナは欠かしてはならない !!
さすがに24時間以内には体温がさがらなかったのですが
丸2日後には見事に36.6(平熱)になりました。
負け惜しみかもしれませんが、まだまだ俺の免疫力は凄いな、と思いました。
ところで・・・
テトラさんと(ステーキ前後も含めて)数年コンタクトが無かったので
私は、すっかり、テトラさんは普通の人間なのだと認識していました。
それは間違いでした。
此処の投稿の「寺田景市」さんの文章に触れ
これだけの長文にもかかわらず見事に展開・構成されている、
こんな文章を日常的にいつも掻けるのはやはり「普通の人間」では無いなと。
少なくても私には絶対に出来ません。
今後とも断片的なコンタクトになってしまうと思いますが
何卒よろしくお願い申し上げます。
Posted by ぶっしゅ at 2023年12月13日 20:28