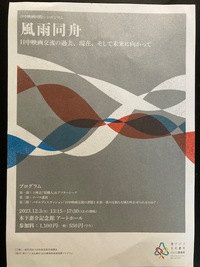2024年05月28日21:01
シネマe~raで「イーちゃんの白い杖 特別編」を観た≫
カテゴリー │映画
3月から5月にかけてシネマe~raで観た映画。
3月30日(土)11時35分~ ビクトル・エリセ監督「瞳を閉じて」
5月3日(土)12時~ 濱口竜介監督「悪は存在しない」
5月26日(日)9時50分~
シネマe~raで橋本真理子監督「イーちゃんの白い杖 特別編」を観た。
この日は上映後、映画に登場する焼津市在住の小長谷一家と音楽の川口カズヒロさんが舞台挨拶で登壇。
元々はテレビ静岡制作のテレビ番組のドキュメンタリー。
1999年、視覚障がいの世界や盲学校の現状を描いた「イーちゃんの白い杖-100年目の盲学校-」から、
25年に渡り継続取材し、作り上げた。
イーちゃんが小学生時代通っていた盲学校は同じ学年がイーちゃんひとり。
先生とマンツーマンの授業が行われる。
天井の高さを知る授業。
机の上に立ち、手を挙げるがまだ届かない。
椅子の高さを把握し、机の上に椅子を積み上げ、
イーちゃんはその上に立つ。
そして、てのひらは天井に届き、
天井というものの姿を知る。
そして、高さというものを身体で知る。
僕だったら、見上げて、ああ、天井だなあで済ましてしまう。
人は自分とあまり関係がないものには、気を留めないものだが、
ビールの缶に点字の表記がある。
イーちゃんこと小長谷唯織さんは、授業の一環でスーパーに出向き、
陳列されているお酒売り場で、いろいろな缶の上部をさわりながら、
「酒かお酒って書いてある」と嬉しそうに言う。
目の不自由な方が、缶飲料で、酒と間違えないようにとの配慮で始まったが、
身近にも点字表記されているものがある。
食料品、電化製品、日用品、信号機、自販機、駅の切符売り場など。
ただし、それに気が付かない。
僕にとって必要ないからだ。
彼女の家族にとっては違う。
共に生活している。
お母さんにとっても。おとうさんにとっても。
おばあちゃん、おじいちゃんにとっても。
外に出る時は、点字ブロックが頼りだ。
お母さんは、イーちゃんが自ら道の進み方を覚えるのを待つ。
手を引っ張れば簡単かもしれないが、何度も迷うのをじっと見守る。
イーちゃんはお母さんに見守られ、行き方を覚える。
弟のイブ君こと小長谷伊吹さんも視覚障がい者だ。
イーちゃんは、白い杖をつき、自分で学校に通うことが出来るが、
イブ君は、出来ない。
イーちゃんよりも障がいは重い。
イーちゃんとイブ君は、互いの顔を見たことがない。
イブ君は音楽が大好きだ。
姉のイーちゃんのピアノ演奏に身体をゆすり、手を合わせ、拍子をとる。
「幸せなら手をたたこう」が大好きだ。
幼稚園の仲間たちが声に出して歌っている中、
イブ君は、心と身体で歌っている。
イーちゃんは小学校は静岡の盲学校、中学は東京の盲学校、
卒業すると浜松の視覚特別支援学校にマッサージ師になるための専門教育を受ける。
住んでいる焼津市から電車に乗り、浜松駅で降り、バスで学校まで通う。
僕もなじみの浜松駅からバスターミナルに続く地下の連絡通路を歩く。
自分の手足であるかのように自在に使う白い杖を突いて。
もちろん自在に見えるのは僕の一方的な思い込みかもしれない。
イーちゃんに直接聞いたこともないのだから。
監督の橋本真理子さんは、テレビ静岡の社員であるが、
小学生の時、お父さんが口腔がんにより、話すことができない障がい者になったことがきっかけで、
記者になることを志す。
「障がい者への偏見をなくしたい」
「障がい者が生きやすい社会にしたい」
その思いが、地方テレビ局の記者として仕事をしながら、
自分のやりたいテーマをさぐる。
30年ほど前、静岡盲学校100周年記念式典の取材時に、
にこにこと目の前を駆けて行ったイーちゃんと出会い、声をかけたのがきっかけだそうだ。
ひとつ質問をすると10の答えが返ってきたとパンフレットの監督のインタビューで語られている。
30年経ち、この日シネマe~raで、東京の盲学校で知り合い結婚した和典さんやイブ君、お父さんお母さんと登壇したイーちゃんは、
まさにそんな感じだった。
イーちゃんは東京での盲学校時代、弱視者と全盲者の違いの中でいじめの体験から、この時期は取材を拒否していた。
その後、和典さんと付き合いはじめ、焼津の実家に遊びに来て、
かつてピアニストを目ざしていたが諦めたイーちゃんのピアノを和典さんがショパンの曲を弾き、
お母さんがめっちゃ上手いじゃんと、感動している姿が美しかった。
舞台挨拶の司会をした橋本監督といかに信頼関係で結ばれているかがよくわかる。
イーちゃんは、これからもよろしくお願いしますと、にこやかに笑う。
取材はまだまだ続く。
31歳になったイブ君、お母さん、お父さんも揃い、
最後は川口カズヒロさんの弾き語りで主題歌「I-あい-」を歌い幕を閉じた。
あいさつ後、何となく元気がなくなったように見えたイブ君は、吹き返し、
音楽にノリノリだった。

3月30日(土)11時35分~ ビクトル・エリセ監督「瞳を閉じて」
5月3日(土)12時~ 濱口竜介監督「悪は存在しない」
5月26日(日)9時50分~
シネマe~raで橋本真理子監督「イーちゃんの白い杖 特別編」を観た。
この日は上映後、映画に登場する焼津市在住の小長谷一家と音楽の川口カズヒロさんが舞台挨拶で登壇。
元々はテレビ静岡制作のテレビ番組のドキュメンタリー。
1999年、視覚障がいの世界や盲学校の現状を描いた「イーちゃんの白い杖-100年目の盲学校-」から、
25年に渡り継続取材し、作り上げた。
イーちゃんが小学生時代通っていた盲学校は同じ学年がイーちゃんひとり。
先生とマンツーマンの授業が行われる。
天井の高さを知る授業。
机の上に立ち、手を挙げるがまだ届かない。
椅子の高さを把握し、机の上に椅子を積み上げ、
イーちゃんはその上に立つ。
そして、てのひらは天井に届き、
天井というものの姿を知る。
そして、高さというものを身体で知る。
僕だったら、見上げて、ああ、天井だなあで済ましてしまう。
人は自分とあまり関係がないものには、気を留めないものだが、
ビールの缶に点字の表記がある。
イーちゃんこと小長谷唯織さんは、授業の一環でスーパーに出向き、
陳列されているお酒売り場で、いろいろな缶の上部をさわりながら、
「酒かお酒って書いてある」と嬉しそうに言う。
目の不自由な方が、缶飲料で、酒と間違えないようにとの配慮で始まったが、
身近にも点字表記されているものがある。
食料品、電化製品、日用品、信号機、自販機、駅の切符売り場など。
ただし、それに気が付かない。
僕にとって必要ないからだ。
彼女の家族にとっては違う。
共に生活している。
お母さんにとっても。おとうさんにとっても。
おばあちゃん、おじいちゃんにとっても。
外に出る時は、点字ブロックが頼りだ。
お母さんは、イーちゃんが自ら道の進み方を覚えるのを待つ。
手を引っ張れば簡単かもしれないが、何度も迷うのをじっと見守る。
イーちゃんはお母さんに見守られ、行き方を覚える。
弟のイブ君こと小長谷伊吹さんも視覚障がい者だ。
イーちゃんは、白い杖をつき、自分で学校に通うことが出来るが、
イブ君は、出来ない。
イーちゃんよりも障がいは重い。
イーちゃんとイブ君は、互いの顔を見たことがない。
イブ君は音楽が大好きだ。
姉のイーちゃんのピアノ演奏に身体をゆすり、手を合わせ、拍子をとる。
「幸せなら手をたたこう」が大好きだ。
幼稚園の仲間たちが声に出して歌っている中、
イブ君は、心と身体で歌っている。
イーちゃんは小学校は静岡の盲学校、中学は東京の盲学校、
卒業すると浜松の視覚特別支援学校にマッサージ師になるための専門教育を受ける。
住んでいる焼津市から電車に乗り、浜松駅で降り、バスで学校まで通う。
僕もなじみの浜松駅からバスターミナルに続く地下の連絡通路を歩く。
自分の手足であるかのように自在に使う白い杖を突いて。
もちろん自在に見えるのは僕の一方的な思い込みかもしれない。
イーちゃんに直接聞いたこともないのだから。
監督の橋本真理子さんは、テレビ静岡の社員であるが、
小学生の時、お父さんが口腔がんにより、話すことができない障がい者になったことがきっかけで、
記者になることを志す。
「障がい者への偏見をなくしたい」
「障がい者が生きやすい社会にしたい」
その思いが、地方テレビ局の記者として仕事をしながら、
自分のやりたいテーマをさぐる。
30年ほど前、静岡盲学校100周年記念式典の取材時に、
にこにこと目の前を駆けて行ったイーちゃんと出会い、声をかけたのがきっかけだそうだ。
ひとつ質問をすると10の答えが返ってきたとパンフレットの監督のインタビューで語られている。
30年経ち、この日シネマe~raで、東京の盲学校で知り合い結婚した和典さんやイブ君、お父さんお母さんと登壇したイーちゃんは、
まさにそんな感じだった。
イーちゃんは東京での盲学校時代、弱視者と全盲者の違いの中でいじめの体験から、この時期は取材を拒否していた。
その後、和典さんと付き合いはじめ、焼津の実家に遊びに来て、
かつてピアニストを目ざしていたが諦めたイーちゃんのピアノを和典さんがショパンの曲を弾き、
お母さんがめっちゃ上手いじゃんと、感動している姿が美しかった。
舞台挨拶の司会をした橋本監督といかに信頼関係で結ばれているかがよくわかる。
イーちゃんは、これからもよろしくお願いしますと、にこやかに笑う。
取材はまだまだ続く。
31歳になったイブ君、お母さん、お父さんも揃い、
最後は川口カズヒロさんの弾き語りで主題歌「I-あい-」を歌い幕を閉じた。
あいさつ後、何となく元気がなくなったように見えたイブ君は、吹き返し、
音楽にノリノリだった。