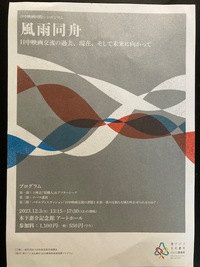2018年06月14日23:41
TOHOシネマズ浜松で「万引き家族」を観た≫
カテゴリー │映画
6月11日(月)20時55分~
レイトショーへ行った。
TOHOシネマズに行くのはひさしぶりかも。
驚いたことにチケット販売所は無人化されていた。
いつの話だ!と突っ込みが来るのかもしれない。
とはいえ、事前に座席を取得する方式はやはり慣れない。
座る場所くらい、
館内に入った時の感覚で選ばせてほしい。
前で観るのか
後ろで観るのか
他のお客さんの配置を見て、
席を確保するのだ。
まあ、もっと行けば慣れることではあるだろう。
マンションの外でじっとしていた
傷だらけの少女を
まるで父と息子のように見える
万引きで一稼ぎしてきたふたりが家に連れてくるところから
話は始まる。
同じ屋根の下に住む人たちは
一見家族のように見える。
祖母であり父であり母であり
姉であり兄である。
そこにまるで妹であるかのように
少女は加わる。
まるで家族のように描かれているが、
ひとりひとりが抱える矛盾の理由は
簡単には明かさない。
家族のように見える人たちの日常を
丹念に描いていく。
そこに映画の時間の多くを費やすが、
それは単にエピソードをつづっているのではない。
ひとりひとりが抱える矛盾を
ひとつひとつ種明かししていく。
この種明かしは
探偵映画のように決して鮮やかではない。
犯人探しが目的ではないし、
わかりやすくエンターテイメントの手法をとっているのでもない。
もともとテレビ等のドキュメント番組を作る会社にいた
是枝監督の特徴なのか、
まるで本当にあったことであるかのように観客に見えるように
カットを選択していく。
すこしずつ解かれていく
種明かしは明るい方向には向かわない。
家族のように見える人たちが
本当の家族ではないのに
一つの屋根の下で住まざるをえなくなった理由
が明かされていく。
ただし、登場人物たちは
みな明るく生き生きとしているように見える。
その生き方は道徳的でもないし、
正しくもないし、
あこがれるものでもない。
倫理観からすると
正しいことをし続ける人は、
ほぼ登場しない。
唯一正しいことをする登場人物は
柄本明さんが演じる駄菓子屋の親父ぐらいだろう。
駄菓子屋の親父が発した一言がきっかけとなり、
物語は終結に向かう。
それぞれが抱えた矛盾が
明らかになるスピードが速まるが
それは喜びではない。
喜びではないが、
不思議とさわやかだ。
そんな中、塀の中で流した安藤サクラさんの涙は
カンヌ映画祭の審査員長の絶賛を浴びたという。
それは、
抱えた矛盾が簡単には解決できないことを象徴する涙だったと思う。
そして、それさえもさわやかで爽快である。
決して、
万引きでつながっている疑似家族を肯定しているわけではない。
かといって、このような状況を生み出す社会に異議を唱えたいのでもない。
ただ、このような人たちがいるかもしれないということを
フィクションとして提示している。
僕もこのような人たちがいるのかもしれないと
心のどこかにとどめる。

レイトショーへ行った。
TOHOシネマズに行くのはひさしぶりかも。
驚いたことにチケット販売所は無人化されていた。
いつの話だ!と突っ込みが来るのかもしれない。
とはいえ、事前に座席を取得する方式はやはり慣れない。
座る場所くらい、
館内に入った時の感覚で選ばせてほしい。
前で観るのか
後ろで観るのか
他のお客さんの配置を見て、
席を確保するのだ。
まあ、もっと行けば慣れることではあるだろう。
マンションの外でじっとしていた
傷だらけの少女を
まるで父と息子のように見える
万引きで一稼ぎしてきたふたりが家に連れてくるところから
話は始まる。
同じ屋根の下に住む人たちは
一見家族のように見える。
祖母であり父であり母であり
姉であり兄である。
そこにまるで妹であるかのように
少女は加わる。
まるで家族のように描かれているが、
ひとりひとりが抱える矛盾の理由は
簡単には明かさない。
家族のように見える人たちの日常を
丹念に描いていく。
そこに映画の時間の多くを費やすが、
それは単にエピソードをつづっているのではない。
ひとりひとりが抱える矛盾を
ひとつひとつ種明かししていく。
この種明かしは
探偵映画のように決して鮮やかではない。
犯人探しが目的ではないし、
わかりやすくエンターテイメントの手法をとっているのでもない。
もともとテレビ等のドキュメント番組を作る会社にいた
是枝監督の特徴なのか、
まるで本当にあったことであるかのように観客に見えるように
カットを選択していく。
すこしずつ解かれていく
種明かしは明るい方向には向かわない。
家族のように見える人たちが
本当の家族ではないのに
一つの屋根の下で住まざるをえなくなった理由
が明かされていく。
ただし、登場人物たちは
みな明るく生き生きとしているように見える。
その生き方は道徳的でもないし、
正しくもないし、
あこがれるものでもない。
倫理観からすると
正しいことをし続ける人は、
ほぼ登場しない。
唯一正しいことをする登場人物は
柄本明さんが演じる駄菓子屋の親父ぐらいだろう。
駄菓子屋の親父が発した一言がきっかけとなり、
物語は終結に向かう。
それぞれが抱えた矛盾が
明らかになるスピードが速まるが
それは喜びではない。
喜びではないが、
不思議とさわやかだ。
そんな中、塀の中で流した安藤サクラさんの涙は
カンヌ映画祭の審査員長の絶賛を浴びたという。
それは、
抱えた矛盾が簡単には解決できないことを象徴する涙だったと思う。
そして、それさえもさわやかで爽快である。
決して、
万引きでつながっている疑似家族を肯定しているわけではない。
かといって、このような状況を生み出す社会に異議を唱えたいのでもない。
ただ、このような人たちがいるかもしれないということを
フィクションとして提示している。
僕もこのような人たちがいるのかもしれないと
心のどこかにとどめる。