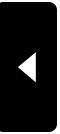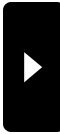2019年11月14日07:54
クリエート浜松2FホールでMUNA-POCKET COFFEEHOUSE「奇跡の街」を観た≫
カテゴリー │演劇
11月10日(日)13時30分~
朝10時から木下恵介記念館で開かれていた
はままつ映画祭2019を観ていた。
昨年もMUNA-POCKET COFFEEHOUSEの公演と日にちが被っていた。
昨年は会場である浜北へ車を走らせたが、
今年は比較的最寄りである
クリエート浜松が会場。
今年は自転車を走らせた。
野田秀樹さんの演出作品にもちろん参加したことなどないが、
ワークショップから稽古が始まるという。
野田さんの作品などはキャスティングに何の苦労もないように思うが、
(だって映画・テレビでひっぱりだこ女優広瀬すずさんを初舞台に立たせるくらいなのだから)
最初は鬼ごっこから始まると出演されたどなたかがかつて笑いながら言っていた。
鬼ごっこかどうかわからないが、
鬼ごっこのように走らされるコミュニケーションをとることを目的とする
ワークショップメニューなのだろう。
ベテランや若手の有名俳優も
演劇初心者向けでもやるようなコミュニケーションゲームから始めるのだという。
それは稽古が台本の本読みから始まるのではないということかもしれない。
本読みから、心理描写や関係性を読み解き、
積み上げていくように芝居を作り上げる。
ワークショップから作り出すということは、
素の役者同志を絡めることにより、
一旦それぞれの名声や経歴をはぎ取り、
作品の名のもとに等しく平等に立場を揃えるところから始めたいという考えではないだろうか。
そこに生まれる期待するものとしては
遊び心というか意識下と言うより無意識下のものなのではないだろうか。
スケジュールが拘束されているプロの役者たちなので、
限られた日程の中で行われる稽古であるにも関わらず、
必要なものとして稽古に組み込まれる。
対して役者を仕事としていない人たちでやる場合、
仕事や勉学や生活の中で稽古時間を捻出しなければならないが、
一方プロたちと違って、自由度がある。
稽古時間が足りないとなれば、
時間を延長したり、
別の日を追加したりと言うことも可能だ。
役者同志が空いてるときに自主稽古、
何て言うのもあり得る。
旗揚げ公演の場合は別にして、
公演を年々積み重ねて行けば、
そのカンパニーのスタイルも確立され、
どこか成熟していくことだろう。
今回のMUNA-POCKET COFFEEHOUSEの公演は
そんなことを感じた。
ダブルキャスト公演はこのカンパニーの特徴であるが、
意図されていたのかどうかはわからないが、
まるでひとつの生き物のように有機的に働いているのではないかと感じた。
2人の未開人がある街に出現した。
しかも発する言葉は2人の間でしか通じない。
この世に2人きりとも言い換えることができる。
2人の発見(出会いと言いたいところだが)により
その街は奇跡の街と呼ばれることになる。
人々は未開人たちと交流を試みようとするが
言葉を理解し合うことはない。
そしてそこは奇跡の街と言うよりも
現代社会の疲弊が現れている
どこにでもあるありふれた街。
また、ひとりひとりがどこにでもいる
ありふれた疲弊した人々。
この芝居は人々の点描により、ただただ現象を伝えている。
永遠にインターンの女子大学生たち、
知的障害を持つ息子と実は虐待している母親、
身体障碍があることを言い訳に何も行動しない自信家、
功績のプレッシャーに負ける博士と何もない助手、
雇われる側の弱者である女性、
女として敗者である女性。
同じ街に住むがそれぞれに濃い関連はない。
それぞれがひとつの点のように生きている。
世界の片隅のそのまた片隅で。
それぞれ認めていないがひっそりと。
否定的に描いているのではない。
あくまでも現象だ。
ひとつだけ関係が逆転し、
希望のように見える場面がある。
すべて相手の言葉をオウム返しで返し、
心のない笑顔ですべてを対処していた女子大生が
心のたけを叫び、相手の心を揺るがせる。
それは自作の歌でギターを弾きながら伝えられる。
「卵の白身じゃない方が好き!」
2人の未開人の内、
1人は死に、
残された1人は自らの言葉が伝えられる相手が
1人もいなくなる。
自らの言葉は自らしかわからない。
人間と言うものは、
わからないのにわかったふりをする。
もしかしたら犬や猫など動物に対してもそうかもしれない。
ひとりではないふりをしたがるのだ。
多分本能だろう。

朝10時から木下恵介記念館で開かれていた
はままつ映画祭2019を観ていた。
昨年もMUNA-POCKET COFFEEHOUSEの公演と日にちが被っていた。
昨年は会場である浜北へ車を走らせたが、
今年は比較的最寄りである
クリエート浜松が会場。
今年は自転車を走らせた。
野田秀樹さんの演出作品にもちろん参加したことなどないが、
ワークショップから稽古が始まるという。
野田さんの作品などはキャスティングに何の苦労もないように思うが、
(だって映画・テレビでひっぱりだこ女優広瀬すずさんを初舞台に立たせるくらいなのだから)
最初は鬼ごっこから始まると出演されたどなたかがかつて笑いながら言っていた。
鬼ごっこかどうかわからないが、
鬼ごっこのように走らされるコミュニケーションをとることを目的とする
ワークショップメニューなのだろう。
ベテランや若手の有名俳優も
演劇初心者向けでもやるようなコミュニケーションゲームから始めるのだという。
それは稽古が台本の本読みから始まるのではないということかもしれない。
本読みから、心理描写や関係性を読み解き、
積み上げていくように芝居を作り上げる。
ワークショップから作り出すということは、
素の役者同志を絡めることにより、
一旦それぞれの名声や経歴をはぎ取り、
作品の名のもとに等しく平等に立場を揃えるところから始めたいという考えではないだろうか。
そこに生まれる期待するものとしては
遊び心というか意識下と言うより無意識下のものなのではないだろうか。
スケジュールが拘束されているプロの役者たちなので、
限られた日程の中で行われる稽古であるにも関わらず、
必要なものとして稽古に組み込まれる。
対して役者を仕事としていない人たちでやる場合、
仕事や勉学や生活の中で稽古時間を捻出しなければならないが、
一方プロたちと違って、自由度がある。
稽古時間が足りないとなれば、
時間を延長したり、
別の日を追加したりと言うことも可能だ。
役者同志が空いてるときに自主稽古、
何て言うのもあり得る。
旗揚げ公演の場合は別にして、
公演を年々積み重ねて行けば、
そのカンパニーのスタイルも確立され、
どこか成熟していくことだろう。
今回のMUNA-POCKET COFFEEHOUSEの公演は
そんなことを感じた。
ダブルキャスト公演はこのカンパニーの特徴であるが、
意図されていたのかどうかはわからないが、
まるでひとつの生き物のように有機的に働いているのではないかと感じた。
2人の未開人がある街に出現した。
しかも発する言葉は2人の間でしか通じない。
この世に2人きりとも言い換えることができる。
2人の発見(出会いと言いたいところだが)により
その街は奇跡の街と呼ばれることになる。
人々は未開人たちと交流を試みようとするが
言葉を理解し合うことはない。
そしてそこは奇跡の街と言うよりも
現代社会の疲弊が現れている
どこにでもあるありふれた街。
また、ひとりひとりがどこにでもいる
ありふれた疲弊した人々。
この芝居は人々の点描により、ただただ現象を伝えている。
永遠にインターンの女子大学生たち、
知的障害を持つ息子と実は虐待している母親、
身体障碍があることを言い訳に何も行動しない自信家、
功績のプレッシャーに負ける博士と何もない助手、
雇われる側の弱者である女性、
女として敗者である女性。
同じ街に住むがそれぞれに濃い関連はない。
それぞれがひとつの点のように生きている。
世界の片隅のそのまた片隅で。
それぞれ認めていないがひっそりと。
否定的に描いているのではない。
あくまでも現象だ。
ひとつだけ関係が逆転し、
希望のように見える場面がある。
すべて相手の言葉をオウム返しで返し、
心のない笑顔ですべてを対処していた女子大生が
心のたけを叫び、相手の心を揺るがせる。
それは自作の歌でギターを弾きながら伝えられる。
「卵の白身じゃない方が好き!」
2人の未開人の内、
1人は死に、
残された1人は自らの言葉が伝えられる相手が
1人もいなくなる。
自らの言葉は自らしかわからない。
人間と言うものは、
わからないのにわかったふりをする。
もしかしたら犬や猫など動物に対してもそうかもしれない。
ひとりではないふりをしたがるのだ。
多分本能だろう。