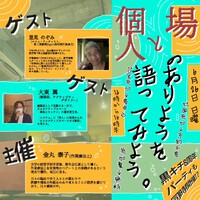2020年12月09日22:31
クリエート浜松で講演会「わたしの城下町浜松~暮らしと美を考える~」後、シネマe~raで「ようこそ映画音響の世界へ」≫
カテゴリー │こんなことあった
浜松街中へ自転車で出かけた。
12月に入っているが、もっと寒くなると
自転車で行くのは躊躇するようになるだろう。
クリエート浜松で講演会を聞いた後、
シネマe~raで映画を観る予定。
はしごするには自転車がちょうどいい。
12月5日(土)13時30分~15時
クリエート浜松2階ホールで、ふじのくに芸術祭2020の記念講演会。
タイトルは「わたしの城下町~暮らしと美を考える」。
講師は木下直之さん。
静岡県立美術館の館長をされている。
木下さんは浜松駅前の薬局(その前は土産物屋)が生家で、
高校卒業まで浜松で過ごされた。
今はもうそこには薬局はない。
浜松城を出発点とした身近な「美」の発見をテーマとした公演。
浜松城周辺を歩き、
彫刻やモニュメントを見つける。
そして街中に足を広げ、
建築物を見つけ、
ゆるキャラを見つける。
長く浜松に住んでいる僕は
紹介されたものの多くを知っていた。
ただし、浜松城公園に残された
「元灰皿」は、
木下さんの個人史に強く根ざした
美であった。
今度浜松城公園に行った際は
さがしてみよう。
そして、
民衆的芸術、民藝運動の話や
今は統合され名のない元城小1.2年の先生から
毎日作文の宿題があり、
蜆塚遺跡へ行ったとき、
「蜆塚遺跡縄文石器文化時代人生活想像図」という
看板を見て、衝撃を受け、
1ページにわたり、作文を書いたというエピソードが語られた。
有楽街に移動し、
15時55分よりシネマe~raで映画鑑賞。
「ようこそ映画音響の世界へ」は
映画における音の歴史を紹介したドキュメント。
映画は「映像」と「音」の二つで出来ている。
映画の半分は音で出来ている。
考えてみればあたりまえのことだが、
普段映画を観ている時は
そのようなことは頭に浮かべない。
どのように音が作られているか
考えながら映画を観る人は僕を含め
そんなにいないだろう。
今回の映画はそのような映画における
音に全面的に焦点を当てた作品。
トーキー映画ができてから、
どの映画にも映像に加えて
音の録音作業が加わった。
つまり、それに携わるスタッフが加わる。
俳優の声を伝える、
音響効果、
音楽、
それぞれコンピューター技術で加工され、
さまざまな状況にふさわしい音が作り出される。
アメリカの映画産業ハリウッドの
現在まで100年の音の歴史を振り返ろうというのだから、
ボリュームは相当なものになる。
それを上映時間94分に詰め込もうというのだから、
観る方が、圧倒されるのも無理はない。
紹介されるのはどれも名作と言われる映画で、
どの作品も音響技術の進化と共に
創られてきたのだと実感する。
しかしながら、観ている最中は
ひとつひとつゆっくり味わう時間もなく、
情報のシャワーを一挙に浴びた
そんな鑑賞後の気持ち。
今まで観た映画の
音の記憶が呼び起こされる。
観ていない映画も一度観たくなる。
観たことがある映画も
もう一度観たくなる。
そんな映画。

12月に入っているが、もっと寒くなると
自転車で行くのは躊躇するようになるだろう。
クリエート浜松で講演会を聞いた後、
シネマe~raで映画を観る予定。
はしごするには自転車がちょうどいい。
12月5日(土)13時30分~15時
クリエート浜松2階ホールで、ふじのくに芸術祭2020の記念講演会。
タイトルは「わたしの城下町~暮らしと美を考える」。
講師は木下直之さん。
静岡県立美術館の館長をされている。
木下さんは浜松駅前の薬局(その前は土産物屋)が生家で、
高校卒業まで浜松で過ごされた。
今はもうそこには薬局はない。
浜松城を出発点とした身近な「美」の発見をテーマとした公演。
浜松城周辺を歩き、
彫刻やモニュメントを見つける。
そして街中に足を広げ、
建築物を見つけ、
ゆるキャラを見つける。
長く浜松に住んでいる僕は
紹介されたものの多くを知っていた。
ただし、浜松城公園に残された
「元灰皿」は、
木下さんの個人史に強く根ざした
美であった。
今度浜松城公園に行った際は
さがしてみよう。
そして、
民衆的芸術、民藝運動の話や
今は統合され名のない元城小1.2年の先生から
毎日作文の宿題があり、
蜆塚遺跡へ行ったとき、
「蜆塚遺跡縄文石器文化時代人生活想像図」という
看板を見て、衝撃を受け、
1ページにわたり、作文を書いたというエピソードが語られた。
有楽街に移動し、
15時55分よりシネマe~raで映画鑑賞。
「ようこそ映画音響の世界へ」は
映画における音の歴史を紹介したドキュメント。
映画は「映像」と「音」の二つで出来ている。
映画の半分は音で出来ている。
考えてみればあたりまえのことだが、
普段映画を観ている時は
そのようなことは頭に浮かべない。
どのように音が作られているか
考えながら映画を観る人は僕を含め
そんなにいないだろう。
今回の映画はそのような映画における
音に全面的に焦点を当てた作品。
トーキー映画ができてから、
どの映画にも映像に加えて
音の録音作業が加わった。
つまり、それに携わるスタッフが加わる。
俳優の声を伝える、
音響効果、
音楽、
それぞれコンピューター技術で加工され、
さまざまな状況にふさわしい音が作り出される。
アメリカの映画産業ハリウッドの
現在まで100年の音の歴史を振り返ろうというのだから、
ボリュームは相当なものになる。
それを上映時間94分に詰め込もうというのだから、
観る方が、圧倒されるのも無理はない。
紹介されるのはどれも名作と言われる映画で、
どの作品も音響技術の進化と共に
創られてきたのだと実感する。
しかしながら、観ている最中は
ひとつひとつゆっくり味わう時間もなく、
情報のシャワーを一挙に浴びた
そんな鑑賞後の気持ち。
今まで観た映画の
音の記憶が呼び起こされる。
観ていない映画も一度観たくなる。
観たことがある映画も
もう一度観たくなる。
そんな映画。