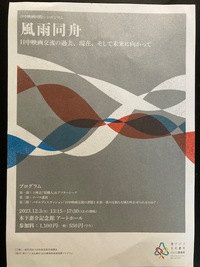2021年11月14日08:50
シネマe~raで「沈黙のレジスタンス ユダヤ孤児を救った芸術家」を観た≫
カテゴリー │映画
11月7日(日)13時55分~
この映画、原題は「RESISTANCE」。
レジスタンスとは辞書で調べると、
「侵略者などに対する抵抗運動。
特に,第二次大戦中ナチス-ドイツ占領下のフランスをはじめとし、
ヨーロッパ各地で組織された地下抵抗運動をいう」
とある。
このタイトルから、パントマイムの第一人者、マルセル・マルソーの話であることは
全く想像できない。
日本での上映時のタイトルは
「沈黙のレジスタンス ユダヤ孤児を救った芸術家」。
マルセル・マルソーを表す言葉(沈黙、芸術家とか)を加えたが、
むしろわかりにくなっていると思う。
映画でのマルソーはとても沈黙どころかとても雄弁だし、
孤児たちを救うこと自体に芸術は全く関係ない。
将来パント・マイムの神様と呼ばれるようになった男が、
ユダヤ人に対するナチの横暴に果敢に抵抗したという話なのだ。
マルソーはチャーリー・チャップリンの映画を観たことがきっかけで、
俳優を志すことになるのだが、
チャップリンも体の動きで表現することも、
当時、音声の録音技術が発達していない
無声映画の時代だったからだと思う。
1923年3月22日生まれのマルソーは、第二次世界大戦の終戦後、
1964年、サラ・ベルナール劇場の中のシャルル・デュランの演劇学校に入る。
この映画で描かれるのは、戦時中のフランス。
ドイツ軍がフランスに侵攻し、
ユダヤ人たちが、粛清されていく。
両親を殺された少女の姿が映し出されるのが映画の冒頭。
一方、マルソーは、
父が経営する精肉店に働きながら、
夜はキャバレーで、パントマイムを披露していた。
ユダヤ人である父親は、芸術なんかで食べていけるかと
俳優になりたいマルソーの夢を否定する。
生活ができないのになぜやるのだ?と問われ、
トイレに行くのと変わらないと答える。
それは、やりたいと体が欲するからだ。
そして、兄アランや従妹ジョルジュ、思いを寄せるエマと共に、
シャルル・ド・ゴールの「自由フランス」という
ドイツによるフランス占領に反対して作られた抵抗組織に入る。
1942年7月21日からは「戦うフランス」と改称された。
そこで、映画の冒頭の親を殺され孤児となった少女を含む
ユダヤ人孤児たちを保護する手伝いをする。
保護してくれる教会に車で連れて行ったとき、
一様に顔を強張らせ、心を閉じていた子供たちを
マルソーはパントマイムの技術を生かし、
一挙に全員を笑顔にさせ、心を開かせる。
また、芸術の道に反対していた父は
追われた疎開先にある舞台で歌を披露する。
訪れたマルソーは父も自分と同じだったことを理解する。
父の夢は歌手になることだったのだ。
孤児たちは、過ごす教会で
讃美歌を歌う。
冒頭の少女は歌がうまく、
映画の後半で、
ユダヤ人を撃退する側の象徴として、マルソーたちを追い詰める
「リヨンの虐殺人」と呼ばれる
クラウス・バルビーの心をほんの少し、和らげる効果を持つ。
マルソーたちが孤児たちを逃がすために乗った列車で、
追うバルビー達の前で絶体絶命ののピンチに陥るが、
逃れるため普段やっていた合唱をするのだが、
バルビーは生まれたばかりの我が娘を思い、
芸術的な素養を身に付けるにはどうしたらいいと必死な思い出
合唱の指揮をするマルソーに聞く。
マルソーは、制限せず、自由にやらせてください、というようなことを答える。
それで納得したかどうかわからないが、バルビーたちは去り、
マルソーたちはピンチを逃れる。
このように、
理不尽な政略者に追い詰められながら抵抗する人々を
「芸術の力」という側面を盛り込みながら描いている。
ただし、映画の全体の構造は、
スリリングで、ドキドキハラハラさせるのだが、
ちょっとうまく作りすぎてんじゃね?
と突っ込みも入れたくなる。
これは、
ポーランド系ユダヤ人、ベネズエラ出身のジョナタン・ヤクボヴィッツ監督の
映画作りのうまさの故の側面ではあるのだが、
ハリウッド映画的だなあと思った。
「逃げるヒーローマルソー、追う悪人バルビー。
さあ、結末はいかに?」
みたいな。
こういう展開の場合、
結末はハッピーエンドでないと観客は納得しない。
ハッピーエンドで安心し満足するのだが、
こういう展開を楽しみに観に来たんだっけ?
とふと思う。
マルソーのパントマイム人生のほとんどは
この映画で描く時間の後から始まる。
僕自身その活動をあまり知らないので
また触れてみたい。

この映画、原題は「RESISTANCE」。
レジスタンスとは辞書で調べると、
「侵略者などに対する抵抗運動。
特に,第二次大戦中ナチス-ドイツ占領下のフランスをはじめとし、
ヨーロッパ各地で組織された地下抵抗運動をいう」
とある。
このタイトルから、パントマイムの第一人者、マルセル・マルソーの話であることは
全く想像できない。
日本での上映時のタイトルは
「沈黙のレジスタンス ユダヤ孤児を救った芸術家」。
マルセル・マルソーを表す言葉(沈黙、芸術家とか)を加えたが、
むしろわかりにくなっていると思う。
映画でのマルソーはとても沈黙どころかとても雄弁だし、
孤児たちを救うこと自体に芸術は全く関係ない。
将来パント・マイムの神様と呼ばれるようになった男が、
ユダヤ人に対するナチの横暴に果敢に抵抗したという話なのだ。
マルソーはチャーリー・チャップリンの映画を観たことがきっかけで、
俳優を志すことになるのだが、
チャップリンも体の動きで表現することも、
当時、音声の録音技術が発達していない
無声映画の時代だったからだと思う。
1923年3月22日生まれのマルソーは、第二次世界大戦の終戦後、
1964年、サラ・ベルナール劇場の中のシャルル・デュランの演劇学校に入る。
この映画で描かれるのは、戦時中のフランス。
ドイツ軍がフランスに侵攻し、
ユダヤ人たちが、粛清されていく。
両親を殺された少女の姿が映し出されるのが映画の冒頭。
一方、マルソーは、
父が経営する精肉店に働きながら、
夜はキャバレーで、パントマイムを披露していた。
ユダヤ人である父親は、芸術なんかで食べていけるかと
俳優になりたいマルソーの夢を否定する。
生活ができないのになぜやるのだ?と問われ、
トイレに行くのと変わらないと答える。
それは、やりたいと体が欲するからだ。
そして、兄アランや従妹ジョルジュ、思いを寄せるエマと共に、
シャルル・ド・ゴールの「自由フランス」という
ドイツによるフランス占領に反対して作られた抵抗組織に入る。
1942年7月21日からは「戦うフランス」と改称された。
そこで、映画の冒頭の親を殺され孤児となった少女を含む
ユダヤ人孤児たちを保護する手伝いをする。
保護してくれる教会に車で連れて行ったとき、
一様に顔を強張らせ、心を閉じていた子供たちを
マルソーはパントマイムの技術を生かし、
一挙に全員を笑顔にさせ、心を開かせる。
また、芸術の道に反対していた父は
追われた疎開先にある舞台で歌を披露する。
訪れたマルソーは父も自分と同じだったことを理解する。
父の夢は歌手になることだったのだ。
孤児たちは、過ごす教会で
讃美歌を歌う。
冒頭の少女は歌がうまく、
映画の後半で、
ユダヤ人を撃退する側の象徴として、マルソーたちを追い詰める
「リヨンの虐殺人」と呼ばれる
クラウス・バルビーの心をほんの少し、和らげる効果を持つ。
マルソーたちが孤児たちを逃がすために乗った列車で、
追うバルビー達の前で絶体絶命ののピンチに陥るが、
逃れるため普段やっていた合唱をするのだが、
バルビーは生まれたばかりの我が娘を思い、
芸術的な素養を身に付けるにはどうしたらいいと必死な思い出
合唱の指揮をするマルソーに聞く。
マルソーは、制限せず、自由にやらせてください、というようなことを答える。
それで納得したかどうかわからないが、バルビーたちは去り、
マルソーたちはピンチを逃れる。
このように、
理不尽な政略者に追い詰められながら抵抗する人々を
「芸術の力」という側面を盛り込みながら描いている。
ただし、映画の全体の構造は、
スリリングで、ドキドキハラハラさせるのだが、
ちょっとうまく作りすぎてんじゃね?
と突っ込みも入れたくなる。
これは、
ポーランド系ユダヤ人、ベネズエラ出身のジョナタン・ヤクボヴィッツ監督の
映画作りのうまさの故の側面ではあるのだが、
ハリウッド映画的だなあと思った。
「逃げるヒーローマルソー、追う悪人バルビー。
さあ、結末はいかに?」
みたいな。
こういう展開の場合、
結末はハッピーエンドでないと観客は納得しない。
ハッピーエンドで安心し満足するのだが、
こういう展開を楽しみに観に来たんだっけ?
とふと思う。
マルソーのパントマイム人生のほとんどは
この映画で描く時間の後から始まる。
僕自身その活動をあまり知らないので
また触れてみたい。