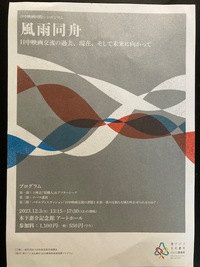2022年02月22日20:47
TOHOシネマズサンストリート浜北で「ウエスト・サイド・ストーリー」を観た≫
カテゴリー │映画
2月18日(土) 20時~
「ウエスト・サイド・ストーリー」はスティーブン・スピルバーグが
1957年にブロードウェイ・ミュージカル版が初演、
1961年にロバート・ワイズ、ジェローム・ロビンズで映画化された作品を再映画化。
何と60年の時を経ている。
脚本に5年かかっているようだが、
エンドロールで、「for dad」とあり、
監督として、また製作や製作総指揮として映画を生み出しているスピルバーグにとり、
「ウエスト・サイド・ストーリー」はお父さんとの思い出を反映する
特別な題材だったのだろう。
初のミュージカル映画を撮影すること、
そして「自らメガホンを握りたい」という思いが詰まっている気がした。
その気合は冒頭からぎゅうぎゅうに詰まっていて、
TOHOシネマズサンストリート浜北 スクリーン8(スクリーンサイズ4.0×9.6m デジタル5.1ch)の
前から5席目を確保して、正解だったなと思いながら観ていた。
初めて事前にインターネットでチケット購入したが、
やはりどの席を取るべきか迷う。
浜松はたぶん全国でもなかなか特殊な地域で、
近隣にTOHOシネマズが
浜松・サンストリート浜北・ららぽーと磐田と3か所もある。
どの場所へ行くのも労力は似たり寄ったりで、
浜松は距離は近いが車停めるのが・・・。
浜北・磐田はどちらも自宅から10キロ程度。
施設情報を見ると、
スクリーンにより客席数もスクリーンサイズもそれぞれ違う。
観やすくて、大スクリーンの迫力もあり音もいい、
そんなベストな席を見つけられるといいが、
それを追求するのは・・・時間がもったいないのでやめておこう。
ただ、他の地域では
IMAX、MX4D、TCX、ATMOS、SCREEN X、轟音
と他に6種もの劇場があるようだ。
映画サイトで「今回はIMAXで観ました!」と
わざわざ言っている方もいるので、
さぞかし、特別感がある劇場なのだろう。
遠回りした。
「ウエスト・サイド・ストーリー」はやっぱりでかい画面、という気分だったので、
前から5番目はよかった。
他の映画の予告映像などが流れているときは、
細かく変わるカットも音もうるさく感じ、
失敗したかなあ、と内心思っていたが、
照明が落ち、映画泥棒が去り、本編が始まると、
不思議とスムーズに集中することができた。
きっとそういう風に考えられているのかもしれない。
ちなみに以前、大の映画好きであるスピルバーグが、
必ず前から6番目までの席で観る、と言っていたのが頭に残っていて、
無意識に前から何番目か数える癖がある。
といいながら、せいぜい5番目よりうしろに座る。
ある映画サイトで、必ず1番前で観る、と言っている方がいたが、
それを試す勇気は今のところない。
「ウエスト・サイド・ストーリー」は
元々はシェイクスピアの「ロミオとジュリエット」を下敷きにしている。
僕は、近頃、DVDで蜷川幸雄演出の演劇とオリビア・ハッセーがジュリエット役をやった映画を観て、
戯曲まで読んだこともあり、映画を観ながら、「ムチャ、ロミオとジュリエットじゃん」と思いながら観たが、
「ロミオとジュリエット」が14世紀のイタリア・ヴェローナのモンタギュー家とキャピレット家の貴族同士の争いを描いているのに対し、
「ウエスト・サイド・ストーリー」は1950年代、再開発で解体されようとしているニューヨークのスラムを舞台にしている。
ポーランド系アメリカ人たちの不良少年グループ・ジェット団とプエルトリコ系アメリカ人たちのシャーク団という
2つのグループが相反している構造は同じだが、こちらはどちらも他国から来た移民たちで、
先住民から言えば、同じマイノリティの立場。
つまり、上と下の争いではない。
下同士の空しい争い。
勝ったからといって、何がどうなるというわけでもない。
本当はもっと立ち向かうことがあるのだろうに。
ただ、方法も知らず、そんな力もない。
そんなどう話が進んでもむなしさしか残らない、
決められた運命のような結末に向かって
物語は突っ走る。
観客たちは、
登場人物たちが起こす数々の過ちに
「バカじゃないの」とやきもきしながら、
若者なら、今の気持ちに、
年配者なら、過去の自分に置き換え、
ま、仕方ないか、と諦める。
観客という者は、
残念なことに画面の流れに従うしかない。
このように物語の構造が揺ぎ無ければ、
あとは絵作りをきっちりこなすしかない。
それはスピルバーグがよくわかっている。
スタッフたちも当然よくわかっている。
何をすればいいのかを。
先ずはミュージカルにもかかわらず、
リアリティーを追求したと思う。
例えば、シャーク団のリーダーで、マリアの兄、ベルナルド役を
1961年版は白人のジョージ・チャキリスが褐色のメイクをして演じて主役以上に人気を博したが、
自らの肌の色が生かせる俳優・デヴィッド・アルヴァレスが演じた。
対立するトニー役のアンセル・エルゴートが長身なこともあり、
身長に差があるが、試合をこなすボクサーという役回りで、
素晴らしいダンス技術を持ちながら、中量級のボクサーという風体で、
主役と対抗する。
画面で対峙したときに身長差を感じながら、ボクサーであることが説得力を持つ。
解体されゆくニューヨークのスラム街の造形はもちろんぬかりない。
街を舞台に緻密に組み立てられ、俳優たちが歌い踊る様子は、
リアリティーを突き抜ける「超ミュージカルで」というべく壮観だ。
ああ、前から5番目でよかった♪
ダンスや歌のシーンはとりわけミュージカルが初めてということもあり、
気合が入っているように見えた。
50年代のパーティ会場のダンスは、とりわけ女性のスカートがクルクルときれいに回っていた。
歌と言えば、ずいぶん前の話だが、
ヒット作を数々出しながら、アカデミー賞が受賞できなかったスピルバーグが
アカデミー賞狙いと言われて作られた「カラーパープル」でのゴスペルシーンを思い出した。
新宿の映画館で見たきりだが、僕がとても好きなシーン。
(その後、1993年に「シンドラーのリスト」で作品賞・監督賞」を受賞する)
そういう意味では、え?スピルバーグがミュージカル?というのはまったくありえなくて、
おそらくどんな種類の映画でも、面白ければなんでも作りたい、というのが永遠の映画少年スピルバーグなのだろう。
ひとつ言えば、
映画でびっくりさせること。
たぶんそれをずっと考えていると思う。
それがスタートからラストまでずっと続けばいい。
もちろん出来ている時もうまくいってない時もあるだろうが。
1961年版で、アルベルトの恋人アニータ役のリタ・モレノが、
若者たちに示唆的なセリフ・歌を歌う重要な役を演じていた。
現在90歳ということだ。
俳優として起用することでレジェンドに敬意を表すると共に、
スピルバーグ自身の思いを投影しているのは間違いないだろう。

「ウエスト・サイド・ストーリー」はスティーブン・スピルバーグが
1957年にブロードウェイ・ミュージカル版が初演、
1961年にロバート・ワイズ、ジェローム・ロビンズで映画化された作品を再映画化。
何と60年の時を経ている。
脚本に5年かかっているようだが、
エンドロールで、「for dad」とあり、
監督として、また製作や製作総指揮として映画を生み出しているスピルバーグにとり、
「ウエスト・サイド・ストーリー」はお父さんとの思い出を反映する
特別な題材だったのだろう。
初のミュージカル映画を撮影すること、
そして「自らメガホンを握りたい」という思いが詰まっている気がした。
その気合は冒頭からぎゅうぎゅうに詰まっていて、
TOHOシネマズサンストリート浜北 スクリーン8(スクリーンサイズ4.0×9.6m デジタル5.1ch)の
前から5席目を確保して、正解だったなと思いながら観ていた。
初めて事前にインターネットでチケット購入したが、
やはりどの席を取るべきか迷う。
浜松はたぶん全国でもなかなか特殊な地域で、
近隣にTOHOシネマズが
浜松・サンストリート浜北・ららぽーと磐田と3か所もある。
どの場所へ行くのも労力は似たり寄ったりで、
浜松は距離は近いが車停めるのが・・・。
浜北・磐田はどちらも自宅から10キロ程度。
施設情報を見ると、
スクリーンにより客席数もスクリーンサイズもそれぞれ違う。
観やすくて、大スクリーンの迫力もあり音もいい、
そんなベストな席を見つけられるといいが、
それを追求するのは・・・時間がもったいないのでやめておこう。
ただ、他の地域では
IMAX、MX4D、TCX、ATMOS、SCREEN X、轟音
と他に6種もの劇場があるようだ。
映画サイトで「今回はIMAXで観ました!」と
わざわざ言っている方もいるので、
さぞかし、特別感がある劇場なのだろう。
遠回りした。
「ウエスト・サイド・ストーリー」はやっぱりでかい画面、という気分だったので、
前から5番目はよかった。
他の映画の予告映像などが流れているときは、
細かく変わるカットも音もうるさく感じ、
失敗したかなあ、と内心思っていたが、
照明が落ち、映画泥棒が去り、本編が始まると、
不思議とスムーズに集中することができた。
きっとそういう風に考えられているのかもしれない。
ちなみに以前、大の映画好きであるスピルバーグが、
必ず前から6番目までの席で観る、と言っていたのが頭に残っていて、
無意識に前から何番目か数える癖がある。
といいながら、せいぜい5番目よりうしろに座る。
ある映画サイトで、必ず1番前で観る、と言っている方がいたが、
それを試す勇気は今のところない。
「ウエスト・サイド・ストーリー」は
元々はシェイクスピアの「ロミオとジュリエット」を下敷きにしている。
僕は、近頃、DVDで蜷川幸雄演出の演劇とオリビア・ハッセーがジュリエット役をやった映画を観て、
戯曲まで読んだこともあり、映画を観ながら、「ムチャ、ロミオとジュリエットじゃん」と思いながら観たが、
「ロミオとジュリエット」が14世紀のイタリア・ヴェローナのモンタギュー家とキャピレット家の貴族同士の争いを描いているのに対し、
「ウエスト・サイド・ストーリー」は1950年代、再開発で解体されようとしているニューヨークのスラムを舞台にしている。
ポーランド系アメリカ人たちの不良少年グループ・ジェット団とプエルトリコ系アメリカ人たちのシャーク団という
2つのグループが相反している構造は同じだが、こちらはどちらも他国から来た移民たちで、
先住民から言えば、同じマイノリティの立場。
つまり、上と下の争いではない。
下同士の空しい争い。
勝ったからといって、何がどうなるというわけでもない。
本当はもっと立ち向かうことがあるのだろうに。
ただ、方法も知らず、そんな力もない。
そんなどう話が進んでもむなしさしか残らない、
決められた運命のような結末に向かって
物語は突っ走る。
観客たちは、
登場人物たちが起こす数々の過ちに
「バカじゃないの」とやきもきしながら、
若者なら、今の気持ちに、
年配者なら、過去の自分に置き換え、
ま、仕方ないか、と諦める。
観客という者は、
残念なことに画面の流れに従うしかない。
このように物語の構造が揺ぎ無ければ、
あとは絵作りをきっちりこなすしかない。
それはスピルバーグがよくわかっている。
スタッフたちも当然よくわかっている。
何をすればいいのかを。
先ずはミュージカルにもかかわらず、
リアリティーを追求したと思う。
例えば、シャーク団のリーダーで、マリアの兄、ベルナルド役を
1961年版は白人のジョージ・チャキリスが褐色のメイクをして演じて主役以上に人気を博したが、
自らの肌の色が生かせる俳優・デヴィッド・アルヴァレスが演じた。
対立するトニー役のアンセル・エルゴートが長身なこともあり、
身長に差があるが、試合をこなすボクサーという役回りで、
素晴らしいダンス技術を持ちながら、中量級のボクサーという風体で、
主役と対抗する。
画面で対峙したときに身長差を感じながら、ボクサーであることが説得力を持つ。
解体されゆくニューヨークのスラム街の造形はもちろんぬかりない。
街を舞台に緻密に組み立てられ、俳優たちが歌い踊る様子は、
リアリティーを突き抜ける「超ミュージカルで」というべく壮観だ。
ああ、前から5番目でよかった♪
ダンスや歌のシーンはとりわけミュージカルが初めてということもあり、
気合が入っているように見えた。
50年代のパーティ会場のダンスは、とりわけ女性のスカートがクルクルときれいに回っていた。
歌と言えば、ずいぶん前の話だが、
ヒット作を数々出しながら、アカデミー賞が受賞できなかったスピルバーグが
アカデミー賞狙いと言われて作られた「カラーパープル」でのゴスペルシーンを思い出した。
新宿の映画館で見たきりだが、僕がとても好きなシーン。
(その後、1993年に「シンドラーのリスト」で作品賞・監督賞」を受賞する)
そういう意味では、え?スピルバーグがミュージカル?というのはまったくありえなくて、
おそらくどんな種類の映画でも、面白ければなんでも作りたい、というのが永遠の映画少年スピルバーグなのだろう。
ひとつ言えば、
映画でびっくりさせること。
たぶんそれをずっと考えていると思う。
それがスタートからラストまでずっと続けばいい。
もちろん出来ている時もうまくいってない時もあるだろうが。
1961年版で、アルベルトの恋人アニータ役のリタ・モレノが、
若者たちに示唆的なセリフ・歌を歌う重要な役を演じていた。
現在90歳ということだ。
俳優として起用することでレジェンドに敬意を表すると共に、
スピルバーグ自身の思いを投影しているのは間違いないだろう。