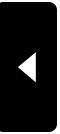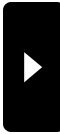2024年02月15日23:31
浜北文化センターでSPAC「伊豆の踊子」を観た≫
カテゴリー │演劇
2月10日(土)13時30分~
原作である川端康成の小説「伊豆の踊子」は映画化、テレビドラマ化、ラジオドラマ化、舞台化などさまざまな形で活用されている。
映画化だけでも、踊子役が田中絹代(1933)、美空ひばり(1954)、鰐淵春子(1960)、吉永小百合(1963)、内藤洋子(1967)、山口百恵(1974)と6度行われている。
作者の川端康成は、1918年の秋、19歳の時、初めて伊豆を旅し、旅芸人の一行と道連れになり、以後10年の間、毎年出かけたと、新潮社文庫本の年譜にある。
短編小説「伊豆の踊子」が発行されたのが1926年1月、27歳の時。
20歳の一高生(現在の東大)が旅先の天城を登る道で雨宿りに寄った茶屋で旅芸人一行と出くわし、
14歳の踊子と恋心を通わせる話。
台本・演出の多田淳之介さんによると、「観光したような気分にもなり、観光に行きたい気分にもなる、その場所やそこにいた人々に思いを馳せてもらえる“観光演劇”を目指した」と、
当日パンフに記されている。
客席の背後から役者が登場したり、「天城越え」や「青い珊瑚礁」やビヨンセやレディ・ガガなどポピュラーな音楽をふんだんに使い、
サービス精神あふれた演劇。
(ラストの曲、良く聴く音楽だったが、曲名を思い出せない‥‥‥)
過去と現代を合わせたようなちょっとやさぐれた旅芸人の衣装、三味線や太鼓の演奏、ミラーボール、ディスコダンスにラップなど、
いろいろ手数を繰り出してきたなあという印象。
抽象的で幅広い言い方だが、『POP(ポップ)』という言葉が、良く当てはまる気がした。
その中で、差別やLGBTQなど古くもあり新しくもあるテーマが盛り込まれている。
それも含め、あふれる雑多感。
それは演出の明確な意図だろう。
入場時には、ピンク色の「踊子シール」まで頂いた。
欲張りな観客たちのために。
舞台上に料亭や旅館の渡り廊下のようなセットが有り、そこで、道行というか、旅をする過程を表現。
背後には、プロジェクターで伊豆の各所の風景や旅館の欄間のような模様が映像で映し出され、舞台美術を補完する。
映像監修は『踊る大捜査線シリーズ』で有名な、映画監督でもある本広克行さん。
映像は使う使わないは別に、現在の演劇表現にとり大きなアイテムとなっているのは間違いないだろう。
映画のCGのように。
セットを降りると、上手や下手は、宿屋や女郎屋や映画館となり、さまざまな場面が演じられる。
僕は下手側の最前列の席だったので、逆の上手側での場面は、とても見にくい。
そのような客席による差別感も演劇と言うジャンルのひとつの特徴。
役者からより近い席をと珍しく最前列を選んだが、うまく行かないところもある。
旅芸人の旅路には途中、所々に「物乞い旅芸人村に入るべからず」という立て札。
このような道を、言いつけ(建前でもある)をきかず大手を振って通ることで、新しい道が開ける。
そんなところが、テーマなのかもしれないと思ってみる。
小説はずいぶん前に読んだが、あまり覚えていなくて、
観劇の勢いで、6作ある映画化された作品の内、
レンタルショップにあった山口百恵版、吉永小百合版、美空ひばり版の3本をまとめて借り、
観てみた。
小説もあらためて読み直した。
一時期、営業の仕事で伊豆方面に車で行っていて、
下田への遠い距離感など、それも今回の観劇に重なった。

原作である川端康成の小説「伊豆の踊子」は映画化、テレビドラマ化、ラジオドラマ化、舞台化などさまざまな形で活用されている。
映画化だけでも、踊子役が田中絹代(1933)、美空ひばり(1954)、鰐淵春子(1960)、吉永小百合(1963)、内藤洋子(1967)、山口百恵(1974)と6度行われている。
作者の川端康成は、1918年の秋、19歳の時、初めて伊豆を旅し、旅芸人の一行と道連れになり、以後10年の間、毎年出かけたと、新潮社文庫本の年譜にある。
短編小説「伊豆の踊子」が発行されたのが1926年1月、27歳の時。
20歳の一高生(現在の東大)が旅先の天城を登る道で雨宿りに寄った茶屋で旅芸人一行と出くわし、
14歳の踊子と恋心を通わせる話。
台本・演出の多田淳之介さんによると、「観光したような気分にもなり、観光に行きたい気分にもなる、その場所やそこにいた人々に思いを馳せてもらえる“観光演劇”を目指した」と、
当日パンフに記されている。
客席の背後から役者が登場したり、「天城越え」や「青い珊瑚礁」やビヨンセやレディ・ガガなどポピュラーな音楽をふんだんに使い、
サービス精神あふれた演劇。
(ラストの曲、良く聴く音楽だったが、曲名を思い出せない‥‥‥)
過去と現代を合わせたようなちょっとやさぐれた旅芸人の衣装、三味線や太鼓の演奏、ミラーボール、ディスコダンスにラップなど、
いろいろ手数を繰り出してきたなあという印象。
抽象的で幅広い言い方だが、『POP(ポップ)』という言葉が、良く当てはまる気がした。
その中で、差別やLGBTQなど古くもあり新しくもあるテーマが盛り込まれている。
それも含め、あふれる雑多感。
それは演出の明確な意図だろう。
入場時には、ピンク色の「踊子シール」まで頂いた。
欲張りな観客たちのために。
舞台上に料亭や旅館の渡り廊下のようなセットが有り、そこで、道行というか、旅をする過程を表現。
背後には、プロジェクターで伊豆の各所の風景や旅館の欄間のような模様が映像で映し出され、舞台美術を補完する。
映像監修は『踊る大捜査線シリーズ』で有名な、映画監督でもある本広克行さん。
映像は使う使わないは別に、現在の演劇表現にとり大きなアイテムとなっているのは間違いないだろう。
映画のCGのように。
セットを降りると、上手や下手は、宿屋や女郎屋や映画館となり、さまざまな場面が演じられる。
僕は下手側の最前列の席だったので、逆の上手側での場面は、とても見にくい。
そのような客席による差別感も演劇と言うジャンルのひとつの特徴。
役者からより近い席をと珍しく最前列を選んだが、うまく行かないところもある。
旅芸人の旅路には途中、所々に「物乞い旅芸人村に入るべからず」という立て札。
このような道を、言いつけ(建前でもある)をきかず大手を振って通ることで、新しい道が開ける。
そんなところが、テーマなのかもしれないと思ってみる。
小説はずいぶん前に読んだが、あまり覚えていなくて、
観劇の勢いで、6作ある映画化された作品の内、
レンタルショップにあった山口百恵版、吉永小百合版、美空ひばり版の3本をまとめて借り、
観てみた。
小説もあらためて読み直した。
一時期、営業の仕事で伊豆方面に車で行っていて、
下田への遠い距離感など、それも今回の観劇に重なった。