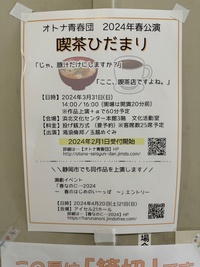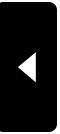2024年05月08日07:32
静岡芸術劇場で「かもめ」を観た≫
カテゴリー │演劇
5月4日(土祝)13時~
チェーホフのかもめを演出家トーマス・オスターマイアーがドイツの劇場ベルリン・シャウビューネにて制作。
2018年に静岡芸術劇場でやはり「ふじのくに⇔世界演劇祭」にて上演されたイプセン「民衆の敵」を僕も観た。
今回のチケットは指定席でなく、まるで小劇場や野外劇場のように整理番号制だった。
その理由は、客席に足を踏み入れて知る。
いつもの客席をつぶし、舞台周辺にパイプ椅子が並べられている。
着席した場所から向かいに座る観客の顔は見え、
三方を観客が囲んだ間に演技スペースがある。
つまり、俳優と観客の距離が近い。
僕はチェーホフの四大劇のひとつ「かもめ」の上演を観たことがない。
ただし、新潮文庫で出ている戯曲は2度読んだ。
ずいぶん前に初めて読んだ時、とても心惹かれた覚えがある。
それは、以前所属していた劇団の主宰者と会う機会があった時、
「かもめ」を読んだことを話に出した記憶がある。
ただし、その後年月とともに内容を忘れてしまった。
そして、もう一度読み直した。
だが、それからも何年も経っている。
そこで今回の観劇。
ドイツ語でしゃべられるとしたら、字幕を見ながらとなる。
「かもめ」は演劇についての話でもあることは間違いがない。
トレープレフは作家志望の青年で、
今までにない新しい表現手段の演劇を作り出そうとしている。
彼が書いた演劇を田舎町の湖のほとりにある家で、訪れている人たちの前で演じるのは女優志望のニーナ。
二人は恋仲のようだが、トレープレフが芸術性にこだわっているのに対し、ニーナは何よりも有名になりたい。
トレープレフの母親のアルカジーナは有名女優。
ただし、息子にとって母が出演する演劇は古典主義の型にはまった旧態依然としたもので、軽蔑さえしている。
そして母の恋人トリゴーリンは、誰もが知る人気小説家。
近頃観た映画でウッディ・アレンの「サンセバスチャンにようこそ」、
ビクトル・エリセの「瞳を閉じて」が、「映画」を題材にした映画だった。
ウッディ・アレン85歳、ビクトル・エリセ82歳発表の作品。
スピルバーグ75歳の作品「フェイブルマンズ」も映画を題材にした自伝的作品。
懐古する年齢なのかとも思うが、
どこか原点に立ち戻ろうという意味合いがあるのではないか?
チェーホフは作家生活の晩年に「かもめ(1896)」「ワーニャ叔父さん(1899~1900」「三人姉妹(1901)」「桜の園(1904)」の四大劇を書いている。
(桜の園が初演されてすぐ1904年に44歳で亡くなっているので、晩年と言っても、かもめが書かれたのは35歳)
「かもめ」を書くことにより、ぐっと劇作家としての世界が広がったと思うのだ。
そういう意味では、「桜の園」後作品が生み出されなくなったのは、何と惜しいことか。
文庫本の池田健太郎さんの解説によると、「かもめ」以前には数編の一幕物、四幕戯曲を三編書いている。
「かもめ」は多幕物の中では第4作で、第3作「森の主」の6年後に書かれ、作劇術は突然目をみはるばかりの成熟ぶりを示したという。
そして、はじめてチェーホフ独特の世界-いわゆるチェーホフ的な静劇の世界-を繰り広げたという。
ここで、演劇を題材にすることで、原点回帰をし、作家として生まれ変わったのではないか?
というのも、演劇(もしくは芸術)に関するセリフには、様々な要素が含まれている。
革新と古典。
夢と後悔。
成功と挫折。
抽象と具体。
自信とうぬぼれ。
本質と虚実。
大衆性と芸術性。
文学と科学。
‥‥‥。
ただし、演劇論を語りたいのではない。
登場人物たちの人間模様、特に恋愛という要素に絡み取られ、話は展開していく。
「演劇」は我が人生に関係ないと豪語する人はいるかもしれないが、
「恋愛」は我が人生に関係ないと言い切れる人はいるのだろうか?
登場人物たちの置かれている立場は様々。
年齢、身分、考え方、肉体、事情など。
それが非常に良く考えられているから、劇中、常にドラマが起こっている。
今回は俳優と観客の距離にこだわった。
だから、あえて立派で快適な座席を使わなかった。
僕たちは普段、用意されているセリフに基づきしゃべっているのではない。
言葉を準備している時もあるかもしれないが、思いついたことを即興で話している。
今回登場する俳優は、そのように思いつきを即興でしゃべっているわけではない。
戯曲があり、稽古があり、その上で舞台にいる。
ただし、さも今思いついたように、セリフをしゃべる。
そんな即興性が活かされた舞台だったと思う。
だから、俳優たちからの発信に目や耳を凝らしていないと、
肝心なことをキャッチできないまま、芝居はどんどん進んでいってしまう。
常に何かを行っているのだ。
仕草・行動だったり、表情だったり。
もちろん役に応じて。
俳優同士の目配りだけでなく、時には観客への目配りも発揮する。
観客の反応を促したり、同意を求めたり。
演劇的効果もふんだんに使われる。
小道具、衣装の他、水や火も使う。
表現の前には遠慮はなく、限りなくどん欲だ。
ボディランゲージも旺盛だ。
というより日常であるのかもしれない。
このあたりは日本で日本人による演劇を観なれていると、生活様式なのか「違い」を思い知らされる。
それにプラスして、一応主人公はトレープレフなのだろうが、
焦点が当てられる人物が次々と変わるのがチェーホフ劇の特徴。
登場人物それぞれの立場に立って、観客も理解しなければならない。
自分が共感できる出来ないに関わらず。
それは決して一方向の考えではなく、ひとつの考えには必ず対論があり、どちらが正解かの答えを与えてくれない。
登場人物が答えがわからず思い、悩み、意見をぶつけ、話し合い、理解し、絶望しと言った行為を、
同時に観客にも行わせるのだ。
だからそこにカタルシスが継続することはない。
水戸黄門で、格さんが紋所を悪党に指し示すと、なだれのように一定のカタルシスが訪れるように。
特定の登場人物に自分を重ねる人もいるだろう。
でも、それも自分と同様、簡単に答えが見つからない人なのだ。
観劇中にそのことに気を取られ、考え事などしていると、話は進んでいってしまうのだ。
状況はすさまじいスピードで展開していく。
ただし、それらを容易に見逃してしまうことも出来る。
そんな風に感じた。
観客も舞台の一員なのだ。
俳優たちと同様に。
マーシャ役の方が、今回の演劇を象徴し、特に体現されているように感じた。
それはカンパニーの中でも若く、マーシャという役割がそうさせたのかもしれない。
役を演じている!という大上段でなく、自分の中に役がある、いや、役の中に自分があるかな?
とにかくそんな感じ。
「ああ、今、楽しい」
素の笑いにそう感じた。
当日配布されたリーフレット「劇場文化」によると、
《演出家の演劇》から距離を置き、俳優に自由が与えられ、自分でセリフを考え、書き直す作業をしたそうだ。
「なるべく原作に忠実にするという条件で、よりパーソナルなものにしてよい」
一言二言しか変えない俳優もいれば、すっかり変える人もいた。
なるほど。
客席で僕も何かをつくりえたのだろうか?
5日、6日も、ふじのくに⇔せかい演劇祭は行われる。
また、毎年行っていたストレンジシードもやっている。
でも、行かないことを決めた。
先月から東京、静岡市と泊りがけで行っていること、
やはり浜松との物理的な距離もある。
自分が手足を動かすことができる行動を優先することにしたのだ。
観ることもつくることであることに間違いはないが、
やはりそれだけでは足りない。
よくある言い方をすれば、
インプットとアウトプットの話だが。

チェーホフのかもめを演出家トーマス・オスターマイアーがドイツの劇場ベルリン・シャウビューネにて制作。
2018年に静岡芸術劇場でやはり「ふじのくに⇔世界演劇祭」にて上演されたイプセン「民衆の敵」を僕も観た。
今回のチケットは指定席でなく、まるで小劇場や野外劇場のように整理番号制だった。
その理由は、客席に足を踏み入れて知る。
いつもの客席をつぶし、舞台周辺にパイプ椅子が並べられている。
着席した場所から向かいに座る観客の顔は見え、
三方を観客が囲んだ間に演技スペースがある。
つまり、俳優と観客の距離が近い。
僕はチェーホフの四大劇のひとつ「かもめ」の上演を観たことがない。
ただし、新潮文庫で出ている戯曲は2度読んだ。
ずいぶん前に初めて読んだ時、とても心惹かれた覚えがある。
それは、以前所属していた劇団の主宰者と会う機会があった時、
「かもめ」を読んだことを話に出した記憶がある。
ただし、その後年月とともに内容を忘れてしまった。
そして、もう一度読み直した。
だが、それからも何年も経っている。
そこで今回の観劇。
ドイツ語でしゃべられるとしたら、字幕を見ながらとなる。
「かもめ」は演劇についての話でもあることは間違いがない。
トレープレフは作家志望の青年で、
今までにない新しい表現手段の演劇を作り出そうとしている。
彼が書いた演劇を田舎町の湖のほとりにある家で、訪れている人たちの前で演じるのは女優志望のニーナ。
二人は恋仲のようだが、トレープレフが芸術性にこだわっているのに対し、ニーナは何よりも有名になりたい。
トレープレフの母親のアルカジーナは有名女優。
ただし、息子にとって母が出演する演劇は古典主義の型にはまった旧態依然としたもので、軽蔑さえしている。
そして母の恋人トリゴーリンは、誰もが知る人気小説家。
近頃観た映画でウッディ・アレンの「サンセバスチャンにようこそ」、
ビクトル・エリセの「瞳を閉じて」が、「映画」を題材にした映画だった。
ウッディ・アレン85歳、ビクトル・エリセ82歳発表の作品。
スピルバーグ75歳の作品「フェイブルマンズ」も映画を題材にした自伝的作品。
懐古する年齢なのかとも思うが、
どこか原点に立ち戻ろうという意味合いがあるのではないか?
チェーホフは作家生活の晩年に「かもめ(1896)」「ワーニャ叔父さん(1899~1900」「三人姉妹(1901)」「桜の園(1904)」の四大劇を書いている。
(桜の園が初演されてすぐ1904年に44歳で亡くなっているので、晩年と言っても、かもめが書かれたのは35歳)
「かもめ」を書くことにより、ぐっと劇作家としての世界が広がったと思うのだ。
そういう意味では、「桜の園」後作品が生み出されなくなったのは、何と惜しいことか。
文庫本の池田健太郎さんの解説によると、「かもめ」以前には数編の一幕物、四幕戯曲を三編書いている。
「かもめ」は多幕物の中では第4作で、第3作「森の主」の6年後に書かれ、作劇術は突然目をみはるばかりの成熟ぶりを示したという。
そして、はじめてチェーホフ独特の世界-いわゆるチェーホフ的な静劇の世界-を繰り広げたという。
ここで、演劇を題材にすることで、原点回帰をし、作家として生まれ変わったのではないか?
というのも、演劇(もしくは芸術)に関するセリフには、様々な要素が含まれている。
革新と古典。
夢と後悔。
成功と挫折。
抽象と具体。
自信とうぬぼれ。
本質と虚実。
大衆性と芸術性。
文学と科学。
‥‥‥。
ただし、演劇論を語りたいのではない。
登場人物たちの人間模様、特に恋愛という要素に絡み取られ、話は展開していく。
「演劇」は我が人生に関係ないと豪語する人はいるかもしれないが、
「恋愛」は我が人生に関係ないと言い切れる人はいるのだろうか?
登場人物たちの置かれている立場は様々。
年齢、身分、考え方、肉体、事情など。
それが非常に良く考えられているから、劇中、常にドラマが起こっている。
今回は俳優と観客の距離にこだわった。
だから、あえて立派で快適な座席を使わなかった。
僕たちは普段、用意されているセリフに基づきしゃべっているのではない。
言葉を準備している時もあるかもしれないが、思いついたことを即興で話している。
今回登場する俳優は、そのように思いつきを即興でしゃべっているわけではない。
戯曲があり、稽古があり、その上で舞台にいる。
ただし、さも今思いついたように、セリフをしゃべる。
そんな即興性が活かされた舞台だったと思う。
だから、俳優たちからの発信に目や耳を凝らしていないと、
肝心なことをキャッチできないまま、芝居はどんどん進んでいってしまう。
常に何かを行っているのだ。
仕草・行動だったり、表情だったり。
もちろん役に応じて。
俳優同士の目配りだけでなく、時には観客への目配りも発揮する。
観客の反応を促したり、同意を求めたり。
演劇的効果もふんだんに使われる。
小道具、衣装の他、水や火も使う。
表現の前には遠慮はなく、限りなくどん欲だ。
ボディランゲージも旺盛だ。
というより日常であるのかもしれない。
このあたりは日本で日本人による演劇を観なれていると、生活様式なのか「違い」を思い知らされる。
それにプラスして、一応主人公はトレープレフなのだろうが、
焦点が当てられる人物が次々と変わるのがチェーホフ劇の特徴。
登場人物それぞれの立場に立って、観客も理解しなければならない。
自分が共感できる出来ないに関わらず。
それは決して一方向の考えではなく、ひとつの考えには必ず対論があり、どちらが正解かの答えを与えてくれない。
登場人物が答えがわからず思い、悩み、意見をぶつけ、話し合い、理解し、絶望しと言った行為を、
同時に観客にも行わせるのだ。
だからそこにカタルシスが継続することはない。
水戸黄門で、格さんが紋所を悪党に指し示すと、なだれのように一定のカタルシスが訪れるように。
特定の登場人物に自分を重ねる人もいるだろう。
でも、それも自分と同様、簡単に答えが見つからない人なのだ。
観劇中にそのことに気を取られ、考え事などしていると、話は進んでいってしまうのだ。
状況はすさまじいスピードで展開していく。
ただし、それらを容易に見逃してしまうことも出来る。
そんな風に感じた。
観客も舞台の一員なのだ。
俳優たちと同様に。
マーシャ役の方が、今回の演劇を象徴し、特に体現されているように感じた。
それはカンパニーの中でも若く、マーシャという役割がそうさせたのかもしれない。
役を演じている!という大上段でなく、自分の中に役がある、いや、役の中に自分があるかな?
とにかくそんな感じ。
「ああ、今、楽しい」
素の笑いにそう感じた。
当日配布されたリーフレット「劇場文化」によると、
《演出家の演劇》から距離を置き、俳優に自由が与えられ、自分でセリフを考え、書き直す作業をしたそうだ。
「なるべく原作に忠実にするという条件で、よりパーソナルなものにしてよい」
一言二言しか変えない俳優もいれば、すっかり変える人もいた。
なるほど。
客席で僕も何かをつくりえたのだろうか?
5日、6日も、ふじのくに⇔せかい演劇祭は行われる。
また、毎年行っていたストレンジシードもやっている。
でも、行かないことを決めた。
先月から東京、静岡市と泊りがけで行っていること、
やはり浜松との物理的な距離もある。
自分が手足を動かすことができる行動を優先することにしたのだ。
観ることもつくることであることに間違いはないが、
やはりそれだけでは足りない。
よくある言い方をすれば、
インプットとアウトプットの話だが。