2021年10月14日23:38
クリエート浜松で「マラー/サド」上映会を観た≫
カテゴリー │いろいろ見た
10月11日(月)17時45分~
2018年10月11日、同じ会場クリエート浜松で、上映会でも演じている演劇集団アルテ・エ・サルーテの「マラー/サド」を観た。
その時の感想はこちら。
https://ji24.hamazo.tv/e8207220.html
本来は昨年2020年、協力団体のある日本の各地でのオーディションで選ばれた人たちも出演して再上演されるはずだったが、
新型コロナウイルスの影響で実施不可能となり、
続く2021年も開催が難しく(なにしろイタリアからやってくるのだ)、
ビデオ上映という形での発表となった。
オーディションで選ばれた人だけでなく、参加した人たちも一緒に練習をし活動してきた。
今回、アルテ・エ・サルーテの上演ビデオには彼らが演じる場面も差し込まれている。
各地の活動拠点で、それぞれ撮影したものだ。
そのような協働作業の上、今回の上映作品は成り立っている。
演劇集団アルテ・エ・サルーテはエミリア・ロマーニャ州立ボローニャ地域保健連合機構精神保健局(ナガッ!)の
患者たちによるプロフェッショナルな劇団。
2000年に設立され、ボローニャ精神保健局と連携し活動を行い、
精神科病院を廃止したイタリアでは、社会活動としての演劇が大きな役割を果たしているということだ。
(チラシより)
イタリア、エミリア・ロマーニャ州の州都であるボローニャは人口38万人、市内にミュゼオ(美術館・博物館・陳列館)が37、
映画館が50、劇場が41、図書館が73あるという。
この記述は、2003年12月に、“30年間の机上の勉強により恋人よりも親しい存在”というくらい
ボローニャを愛する井上ひさしさんが、
NHKの番組のために依頼された2週間の取材旅行の際に書いた「ボローニャ紀行」という本に掲載されている。
第二次世界大戦後、イタリアでは、キリスト教民主党と共産党の二大政党が対抗していて、
中央権力は右派のキリスト教民主党の手中にあり、中央政権は、復興のための資金を
政敵であるボローニャに回さないように画策したりの露骨なボローニャいじめをした。
ただし、その後、ボローニャはイタリアでも指折りの裕福な都市となるが、
中央政府と五分に争うまでに成長した自分たちの力量を、たとえば「演劇」で表現できないかと考えた。
「自分がいま生きている場所を大事にしよう。この場所さえしっかりしていれば、人はなんとかしあわせに生きていくことが出来る」
というボローニャ人の熱い思いを舞台に再現して、目に見えるものにしようと思い立つ。
演劇が、演劇を好きな人たちのための楽しみのためだけでなく、
目に見えないものを見えるものに変える力があり、
つまり未来の姿を映し出す鏡のような役割を持つ。
演劇集団アルテ・エ・サルーテの存在もそのようなボローニャの環境と無縁ではないように思う。
通常なら、患者が集まれば、病気を治すということのみのつながりしか持たない。
例えば病院とはそういう場所だ。
それ以上の役割は持たない。
ただし、病気は病気として受け入れたうえで、
それを越えて、
自分たちの置かれている状況(患者という立場である自分をも)や
今自分たちが考えていることを演劇という形で表し、
世に提示することで、
あるべき社会を指し示すことになるのではないか。
このように考えると誰もが演劇をやる資格を持つことになる。
専門家であることはあまり関係ない。
地域でのそれぞれの立場、
職場でのそれぞれの立場、
家庭でのそれぞれの立場、
それぞれの個人としての立場で、
演劇をやる理由があるのではないか。
だからと言って誰にでもこの日、または2018年10月に観たような作品ができるわけではない。
そこには様々なサポートする人たちがいることを忘れてはならない。
上映後に
リモートを活用したトークセッションがあった。
最後に会場から「続けていくには助け合いが必要」という意見があった。
確かにその通りで、
助け合うことが出来るような形にどのようにするか?はいつも課題だ。
資金が必要ならそれをどうするか?
人(技術)が必要ならそれをどうするか?

2018年10月11日、同じ会場クリエート浜松で、上映会でも演じている演劇集団アルテ・エ・サルーテの「マラー/サド」を観た。
その時の感想はこちら。
https://ji24.hamazo.tv/e8207220.html
本来は昨年2020年、協力団体のある日本の各地でのオーディションで選ばれた人たちも出演して再上演されるはずだったが、
新型コロナウイルスの影響で実施不可能となり、
続く2021年も開催が難しく(なにしろイタリアからやってくるのだ)、
ビデオ上映という形での発表となった。
オーディションで選ばれた人だけでなく、参加した人たちも一緒に練習をし活動してきた。
今回、アルテ・エ・サルーテの上演ビデオには彼らが演じる場面も差し込まれている。
各地の活動拠点で、それぞれ撮影したものだ。
そのような協働作業の上、今回の上映作品は成り立っている。
演劇集団アルテ・エ・サルーテはエミリア・ロマーニャ州立ボローニャ地域保健連合機構精神保健局(ナガッ!)の
患者たちによるプロフェッショナルな劇団。
2000年に設立され、ボローニャ精神保健局と連携し活動を行い、
精神科病院を廃止したイタリアでは、社会活動としての演劇が大きな役割を果たしているということだ。
(チラシより)
イタリア、エミリア・ロマーニャ州の州都であるボローニャは人口38万人、市内にミュゼオ(美術館・博物館・陳列館)が37、
映画館が50、劇場が41、図書館が73あるという。
この記述は、2003年12月に、“30年間の机上の勉強により恋人よりも親しい存在”というくらい
ボローニャを愛する井上ひさしさんが、
NHKの番組のために依頼された2週間の取材旅行の際に書いた「ボローニャ紀行」という本に掲載されている。
第二次世界大戦後、イタリアでは、キリスト教民主党と共産党の二大政党が対抗していて、
中央権力は右派のキリスト教民主党の手中にあり、中央政権は、復興のための資金を
政敵であるボローニャに回さないように画策したりの露骨なボローニャいじめをした。
ただし、その後、ボローニャはイタリアでも指折りの裕福な都市となるが、
中央政府と五分に争うまでに成長した自分たちの力量を、たとえば「演劇」で表現できないかと考えた。
「自分がいま生きている場所を大事にしよう。この場所さえしっかりしていれば、人はなんとかしあわせに生きていくことが出来る」
というボローニャ人の熱い思いを舞台に再現して、目に見えるものにしようと思い立つ。
演劇が、演劇を好きな人たちのための楽しみのためだけでなく、
目に見えないものを見えるものに変える力があり、
つまり未来の姿を映し出す鏡のような役割を持つ。
演劇集団アルテ・エ・サルーテの存在もそのようなボローニャの環境と無縁ではないように思う。
通常なら、患者が集まれば、病気を治すということのみのつながりしか持たない。
例えば病院とはそういう場所だ。
それ以上の役割は持たない。
ただし、病気は病気として受け入れたうえで、
それを越えて、
自分たちの置かれている状況(患者という立場である自分をも)や
今自分たちが考えていることを演劇という形で表し、
世に提示することで、
あるべき社会を指し示すことになるのではないか。
このように考えると誰もが演劇をやる資格を持つことになる。
専門家であることはあまり関係ない。
地域でのそれぞれの立場、
職場でのそれぞれの立場、
家庭でのそれぞれの立場、
それぞれの個人としての立場で、
演劇をやる理由があるのではないか。
だからと言って誰にでもこの日、または2018年10月に観たような作品ができるわけではない。
そこには様々なサポートする人たちがいることを忘れてはならない。
上映後に
リモートを活用したトークセッションがあった。
最後に会場から「続けていくには助け合いが必要」という意見があった。
確かにその通りで、
助け合うことが出来るような形にどのようにするか?はいつも課題だ。
資金が必要ならそれをどうするか?
人(技術)が必要ならそれをどうするか?

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
|
|




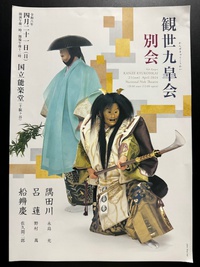


書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。