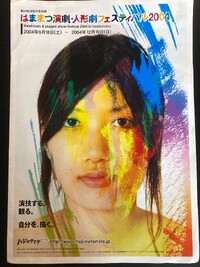2017年08月09日06:19
劇作のきっかけ≫
カテゴリー │静岡県西部演劇連絡会会報原稿
■劇作のきっかけ
フィールド 寺田景一
劇作ワークショップが、今年もこの夏行われる。
さて、僕が戯曲というものを書き始めたのはいつのことだろう。
振り返ると、多分、小学校の時のお楽しみ会の出し物で、同じクラスの何人かとごく短い演劇のようなものを発表した時ではないだろうか。
お楽しみ会とは学芸会と言われるものと同義語。
当時、家族で名古屋に旅行か何かで行ったとき、名古屋駅の近くで初めて目にした乞食に衝撃を受け、乞食を登場人物とした戯曲を僕が書いた。
浜松でもホームレスの姿を目にするのは珍しくはない。
でもその頃は、テレビなどで「右や左の旦那様あわれな乞食にお恵みを」という常套句と共に、知っていたが、実際に目の当たりにしたことはなかった。
休み時間や放課後の友達同士の会話でも乞食のネタはよく出現した。
「この乞食~!」と乞食ではない同級生を馬鹿にしたり揶揄したり。
無理に分析すれば、小学生の子供という、大人が幅をきかす人間世界でも下層の立場ながら、できるだけ目下の、さげすむことが出来る安心な対象を見つけて、日頃の鬱屈の代替行為とする。
例えば小動物や弱いものをいじめたり虐げたりと同様。
今はむしろホームレスの方々は公共の場をうまく使い、居住地を確保し、悠々と生きているようにも見える。
昔は乞食と言うものは、空き缶を目の前に置いて、金(お恵み)をねだったものだ。
物乞いという行為だ。
今はそんな姿はあまり見ない。
援助するボランティア団体が充実してきたのか、飽食の時代でコンビニや飲食店の残飯が容易にありつけるのか。
それらもあるが、街頭で空き缶を置き、みすぼらしい格好をして座っていても、よけて通るのみで、金を入れる人などいなくなったのではないだろうか。
僕が書いた戯曲は、乞食が何人か登場する。
お楽しみ会の発表は教室の一番前を少しスペースを空けて、行われる。
何人かの乞食は互いに間隔を空けて、横並びに座っている。
そして、それぞれの目の前に空き缶が置いてある。
そこに1人の通行人が通る。
何か乞食に呼びかける。
乞食は「へん」と答える。
「へん」というのはその頃クラスで流行っていた言葉で、「返事をしない」という意味の返事であった。
つまり、無視している、相手にしていない、という意思表示の言葉だ。
通行人は乞食それぞれに呼びかけるが、皆、「へん」という返事をするのみ。
クラスのみんなは大爆笑であったのであろうか。
「へん」は確実にクラスの流行り言葉であったから、ウケた確率は高い?
ずいぶん昔のことだ。
上演の場面の記憶もない。
誰とやったのかも記憶にない。
記憶にあるのはコミュニケーション不全の物語の戯曲のおぼろげな概要のみ。
小6の林間学校で、クラス毎で何かを発表したが、白雪姫をパロディにした戯曲を書いた。
魔女が白雪姫に毒リンゴを食わせるのを、なぜか屋台で毒ラーメンを食わせた。
以後、多いとは言えないが、いくつかの戯曲を書き、今に至る。
関係ないが、ベケットの「ゴドーを待ちながら」は、浮浪者2人がメインの登場人物。
ちなみに「乞食」という言葉は、今では、電波媒体では放送禁止用語。
また、本来は仏教用語で「托鉢」の意味。
(2017年8月6日号静岡県西部演劇連絡会 会報より)
写真は文章の内容とは関係のない7月の終盤、仕事で南伊豆方面へ行った時、
思わず車を停めて撮った海。
この先には、伊豆七島がある。
世間の学校では夏休みが始まった頃。

フィールド 寺田景一
劇作ワークショップが、今年もこの夏行われる。
さて、僕が戯曲というものを書き始めたのはいつのことだろう。
振り返ると、多分、小学校の時のお楽しみ会の出し物で、同じクラスの何人かとごく短い演劇のようなものを発表した時ではないだろうか。
お楽しみ会とは学芸会と言われるものと同義語。
当時、家族で名古屋に旅行か何かで行ったとき、名古屋駅の近くで初めて目にした乞食に衝撃を受け、乞食を登場人物とした戯曲を僕が書いた。
浜松でもホームレスの姿を目にするのは珍しくはない。
でもその頃は、テレビなどで「右や左の旦那様あわれな乞食にお恵みを」という常套句と共に、知っていたが、実際に目の当たりにしたことはなかった。
休み時間や放課後の友達同士の会話でも乞食のネタはよく出現した。
「この乞食~!」と乞食ではない同級生を馬鹿にしたり揶揄したり。
無理に分析すれば、小学生の子供という、大人が幅をきかす人間世界でも下層の立場ながら、できるだけ目下の、さげすむことが出来る安心な対象を見つけて、日頃の鬱屈の代替行為とする。
例えば小動物や弱いものをいじめたり虐げたりと同様。
今はむしろホームレスの方々は公共の場をうまく使い、居住地を確保し、悠々と生きているようにも見える。
昔は乞食と言うものは、空き缶を目の前に置いて、金(お恵み)をねだったものだ。
物乞いという行為だ。
今はそんな姿はあまり見ない。
援助するボランティア団体が充実してきたのか、飽食の時代でコンビニや飲食店の残飯が容易にありつけるのか。
それらもあるが、街頭で空き缶を置き、みすぼらしい格好をして座っていても、よけて通るのみで、金を入れる人などいなくなったのではないだろうか。
僕が書いた戯曲は、乞食が何人か登場する。
お楽しみ会の発表は教室の一番前を少しスペースを空けて、行われる。
何人かの乞食は互いに間隔を空けて、横並びに座っている。
そして、それぞれの目の前に空き缶が置いてある。
そこに1人の通行人が通る。
何か乞食に呼びかける。
乞食は「へん」と答える。
「へん」というのはその頃クラスで流行っていた言葉で、「返事をしない」という意味の返事であった。
つまり、無視している、相手にしていない、という意思表示の言葉だ。
通行人は乞食それぞれに呼びかけるが、皆、「へん」という返事をするのみ。
クラスのみんなは大爆笑であったのであろうか。
「へん」は確実にクラスの流行り言葉であったから、ウケた確率は高い?
ずいぶん昔のことだ。
上演の場面の記憶もない。
誰とやったのかも記憶にない。
記憶にあるのはコミュニケーション不全の物語の戯曲のおぼろげな概要のみ。
小6の林間学校で、クラス毎で何かを発表したが、白雪姫をパロディにした戯曲を書いた。
魔女が白雪姫に毒リンゴを食わせるのを、なぜか屋台で毒ラーメンを食わせた。
以後、多いとは言えないが、いくつかの戯曲を書き、今に至る。
関係ないが、ベケットの「ゴドーを待ちながら」は、浮浪者2人がメインの登場人物。
ちなみに「乞食」という言葉は、今では、電波媒体では放送禁止用語。
また、本来は仏教用語で「托鉢」の意味。
(2017年8月6日号静岡県西部演劇連絡会 会報より)
写真は文章の内容とは関係のない7月の終盤、仕事で南伊豆方面へ行った時、
思わず車を停めて撮った海。
この先には、伊豆七島がある。
世間の学校では夏休みが始まった頃。